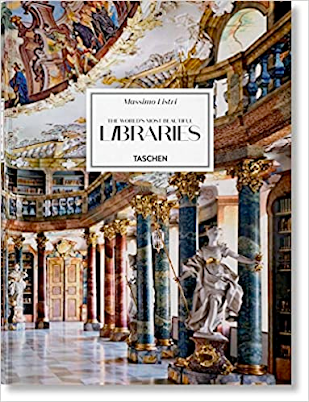書いている時点ではまだ刊行されていないが、石井光太『ルポ 誰が国語力を殺すのか』(文藝春秋刊)が7月末に刊行予定である。この本を版元から頂いたので一読した感想を記しておきたい。頂いたのはこの本のなかで著者によるインタビューがあって私の発言の一部が引用されているからである。
本書の概要
本書でいう国語力であるが、一般的には本を読むための読解力とか言語力のようなコンテクストにおいて理解されている。PISAの読解力(reading literacy)の点数が他のリテラシーよりも低いとか、大学生が中学校の教科書を正しく読めない(あのクイズまがいの質問にこたえられないことが読解力がないことの根拠に使われていたのには少々あきれたが)、大学生の半数は1ヶ月に1冊の本も読んでいないといった言説で言われるものである。が、本書で扱う国語力の幅はもう少し広い。というよりも、国語力とは言葉を使用する能力であり、言葉が人間の営みのもっとも基本にあるものとすれば、国語力の低下とは人間の営みが損なわれている状態だという、至極もっともな前提から始まり、前半はそこに焦点が当たっている。
冒頭には小学校4年生の授業で新美南吉『ごんぎつね』が取り扱われたシーンが紹介されている。その部分が「立ち読み」できるので参照されたい。子狐のごんは猟師兵十(ひょうじゅう)に悪さを仕掛けていたが、兵十の母親の葬儀がありそこで大なべにぐらぐらと湯が沸き立っているのを見かけるというシーンである。ストーリーはこのシーンをきっかけにごんは兵十が病気の母親に精のつくものを食べさせようとしていたことを悟り、逆に兵十に魚を届けるのだが最後に兵十に撃たれてしまうというものである。大人にとっても子どもにとってもストーリーはなかなか理解に苦しむものではあるけれども、個々のシーンは分かりやすい。そのなかで、教師は子どもたちを班に分けて鍋で何を煮ているのかと尋ねる。子どもたちは「兵十の母の死体を消毒している」「死体を煮て溶かしている」と答えたというのである。『ごんぎつね』でなぜこのシーンを議論させるのかという疑問もあるが、子どもたちの生活実感と教材の世界のあいだのズレを考えさせられる。
この話しを出発点にして、こどもの言語生活がいかに家庭環境そして、ネット、ゲームなどのメディア環境によって蝕まれているかについて論を展開している。たとえばゲームのプレイヤーどうしのことばのやりとりは「死ね」「ぶっ殺せ」「ざけんじゃねぇ」「帰れ、カス」というもの発しているだけで会話になっていない。そのことはSNS上で「あいつまじないわ」「きも」「きも」「さよーなーら」といった書き込みの連鎖につながっている。また、家庭環境についてはそうした言語生活を誘発するものになっていることが描かれる。不登校で一人家にいる状態、離婚による一人親に放課後放っておかれる状態、親の再婚で他の家族から疎まれる状態、ヤングケアラーと呼ばれる親の介護を余儀なくされる状況等々である。
本書の帯についている紹介文に「オノマトペでしか自分の罪を説明できない少年たち、交際相手に恐喝されても被害を認識できない女子生徒」という文がある。折り合いの悪い義父に呼び出されて外に飛び出しナイフで他人を刺した少年の話。「よくわかんない。あいつのせいで頭グリグリになった。目の前に人がいたんでバァーってやったんだ。...警察にガッってされてつれていかれた。」少女売春の少女との会話。「ー男たちに金を払ったのはなぜ?」「言われたから...サンキューって言ってくれる人もいた」「売春は嫌だった?」「そうだけど、他にすることもないし」「後悔してる?」「わかんない」これらは、少年院や福祉施設の職員に対して自分の置かれている立場を言葉で説明することができないことを指している。かつての「不良」や「非行」の少年少女は自分の行動に対する言葉をもち、仲間と会話していたが、今のそうした子どもたちの多くが孤独で、短く感情的な言葉を発し後は押し黙るだけだというのである。
本書はその背後に日本社会の経済格差があり、貧困家庭が増えていることを指摘する。つまり、言葉が貧困になっているのは家庭生活が貧困であるからで、本来、家庭のなかで基本的な会話や表現を学ぶ機会がないままに大人になっていくケースが増えている。そして、メディア環境がそこに忍び込み、ゲームやSNSにおける言葉を伴わない、ないしは短い言葉によるメディア上のやりとりで自足するような状況があることを述べている。家庭がもっとも基盤的な子どもたちの生育環境のはずなのに機能せず、さらに地域社会や学校社会から孤立化を進行させるときに、メディアが唯一の救いになるような状況は確かにあるだろう。さらには、メディア環境がサイバーカスケードないしエコーチェンバーのように、特定のコミュニティ内で自足しそのままそれが支配的なものを形成することがあり、未発達の子どもたちに強い影響を与えるのは大人とは区別して考える必要がある。著者は、特定のメディア環境が脳の発達に対して及ぼす影響についても言及している。
こういう状況に対する著者の処方箋の一つは、少年院で行われている「表現教育」と呼ばれる言語回復プログラムである。たとえばアンジェラ・アキの『手紙〜背景 十五の君へ〜』を朗読させ、現在の自分から将来の自分に宛てた手紙を書くというプログラムがある。先輩が読む手紙を聞いている少女たちは一様に感動の涙を流すという。また、小学校のプログラムとしては、積極的に本を読ませるが、と同時に体験型学習に力を入れてキャンプ、宿泊体験といったものだけでなく校外の自然環境を教材としてそこから学ばせる。また、教科を超えたアクティブラーニングを積極的に実施することで、本で読んで得た知識と実際の世界との関係のリンクをしっかりもたせることを行う。中高生の授業では言葉によるやりとりを重視したプログラムとして、ディベートや哲学的対話を導入している学校が紹介されていた。
感想
普段、学術的な文章ばかり読んでいてこうした一般向けのルポルタージュの文章を読む機会はあまりないから、本書を読んでみてプロのライターの取材力と文章力には驚かされた。これまでも国語の問題には注意を払ってきたつもりだが、このように家庭崩壊やいじめの問題、非行や少女売春といった社会問題にまで視野を拡げた文章はこういう機会でもないと読めないものだった。その意味で読む価値がある力作だと感じた。
以前に私自身国語教育について朝日新聞(2020年4月4日朝刊)の「耕論」欄でインタビューを受けて発言もしている。インタビューの依頼はそれに基づくのだろう。そのときは、日本の国語力が文学の読みに典型的な書き手の気持ちに寄り添い、その心情を適切に読み取って言葉で表現する力を要求してきたのではないかと述べた。他方、PISAの読解力の低下が示されたあとに論理国語の重要性が言われ、それが文学国語が対立するという議論があることに対して、文学にも論理はありそれを読み取ることについては論理国語のなかに包摂されるとも考えていた。私はすべての学力の基礎に国語力(言語力)があると考えていたので、この本がどのような展開と結論になるのかに興味をもっていた。
そうした興味に照らしてみると本書の意義と弱点が浮かび上がってくる。意義は、私もあまり意識していなかった国語力と生活力の関係を格差社会のコンテクストで浮かび上がらせてくれたことである。要するに義務教育で日常生活に必要なレベルの国語力が身につかないままに社会に放り出されている子どもたちがたくさんいることへの着目だ。そのことはさまざまな具体的な局面で論じられており、また、その対策としての少年院における表現教育のような事例が示されていて説得力がある。つまり、マイナスの生活力でスタートした子どもたちに対する事後的な救済プログラムが示されているわけだ。国語力の向上が生活力につながるという見方には大賛成だ。
最初の『ごんぎつね』のエピソードに意味をもたせるとすれば、子どもたちはすでに村の共同葬儀に参加する機会がもてないし、亡くなった人の遺体の処理がどのように行われるのかを見聞きする機会もないことをどのようにとらえるかが重要である。知識も経験もない子どもたちにとってこの部分だけを取り出して議論させられれば、上記のような反応が出てくる可能性は十分にある。このエピソードの後に教師がどのように指導したのかが示されていないので分からないのだが、本筋でない部分の子どもたちの反応がこのように現れたことから、昔の習慣や遺体処理ということについて考えるきっかけにすべきなのか、それとも古典的名作童話とされる話しがすでに教材として古いから差し替えるべきと考えるのか。また、ごんが兵十にしかけたいたずら、ごんから見た兵十と母親の関係、そしてごんの好意が仇になったことをどのように指導すべきなのかも気になった。国語が生活そのものと結びついているとすれば、このストーリーからは社会の荒波や人生の皮肉も学ぶべきなのだろうか。あるいは自己犠牲の精神のようなものをほのめかすのだろうか。古典とされる作品はさまざまな読み方を許すわけで、それが読み手が確認できればよいのだろうが、そのレベルの指導をじっくり行うことはなかなか難しいように感じる。(あるいは指導法にも定石があるのか。)
国語の意義を積極的に位置付けようとすれば何が可能であろうか。かつてこのブログで朝読(朝の読書の時間)が形骸化しつつあるのではないかと述べたことがある(「子どもの本離れは解消されたのか — 飯田一史『いま、子どもの本が売れる理由』を読む」)。子どもたちにとっては勝手に好きな本を読む時間を設けるだけでは、本好きな子とそうでない子との間の差は埋めることができない。本書の前半に経済格差と教育格差の問題が述べられていたが、本への関心はすでにそれ以前の親の関心の違いによってつくられているのだから、ここには積極的な介入プログラムを導入する必要があるのではないか。たとえば、本書で述べられているような国語科を中心としたアクティブラーニングとも言うべきものが可能かもしれない。これは戦後間もないときに試みられたコア・カリキュラムの考え方とも近い。もっとも当時は社会科が中心とされたが。
だが、本書の最後の方で紹介されているのはカリキュラム上の工夫をしている学校の話しだが、公立校ではない。だから、経済格差が陰のテーマとなっている本書で読みたかったのは、やはり公立小学校レベルで生活力につながるような国語の授業ないし読書推進の試みをしている学校の事例である。国語の問題が生活や社会の問題とつながっているという認識はあまり一般的ではない。子どもの発達が就学前に家庭で育まれ、就学後は学校と家庭の総合的関係のなかで決定される。格差社会が現実のものであれば、子どもたちの生きていくための力が失われている状態に対して国語を中心としたカリキュラムの工夫が必要となる。家庭の方に問題がある事例が増えている現在、学校において基礎的な国語力をまず身につけさせるための手立てを考えていく時期にきている。