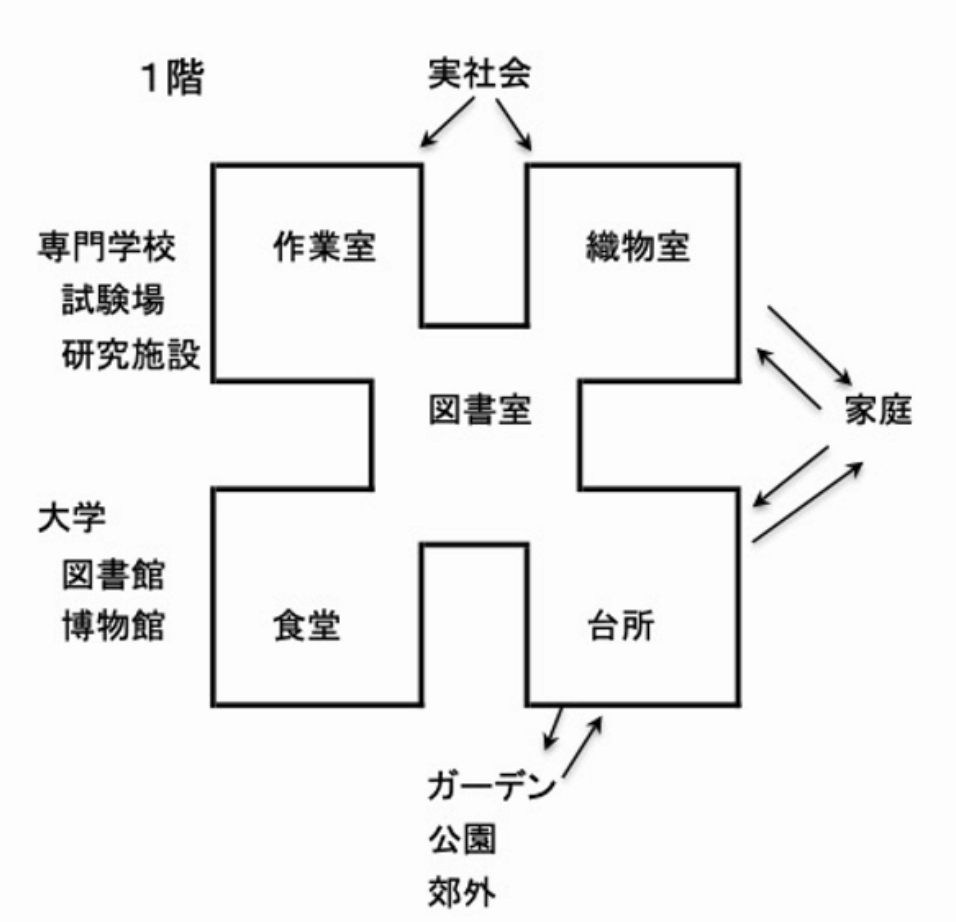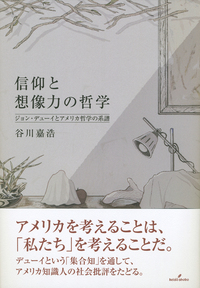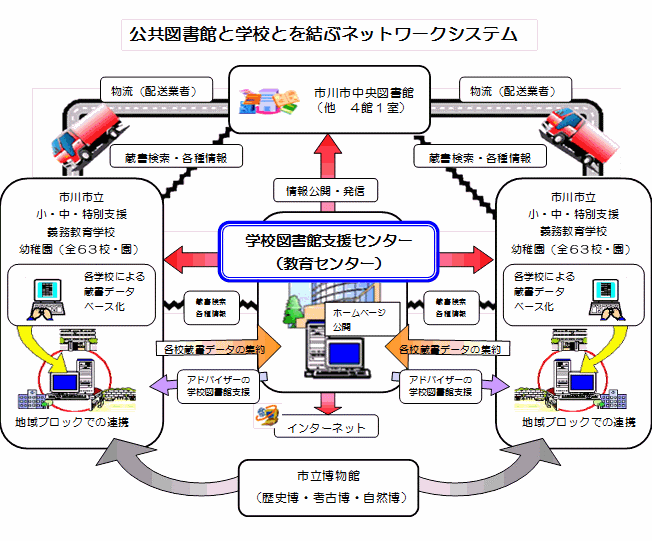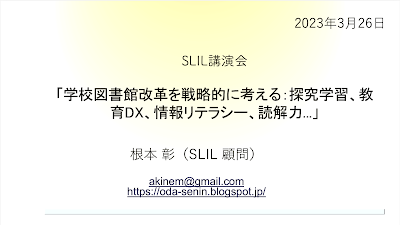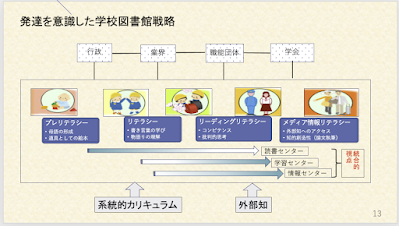以下、最近、いくつかの図書館を訪ねて、それらに通底する戦後図書館の論理と限界、そして可能性を感じたので書いておきたい。このブログでは公共図書館の運営と今後の在り方について、あまり前面に出して論じてこなかったことではあるが、いい機会なので備忘録としておく。
函館・天理・野田興風
5月下旬に函館市立中央図書館と旧市立函館図書館を訪ねた。ここの初代館長岡田健蔵は、明治末期にできた私立函館図書館の設立者で市立図書館となってから長らく館長を務め、市会議員もしていた地元の有名人である。彼が北方資料にこだわり、その方面で有数のコレクションをつくったことは図書館史家の間では知られていたが、全国的に有名というわけではない。同図書館は現在はTRCと地元企業との共同で指定管理になっている。やはり民間になじみやすいところなのかもしれない。
旧市立函館図書館(現中央図書館とは別)
6月に関西旅行をしたときに、天理図書館を訪ねた。天理教2代目真柱で同教発展の立役者中山正善の事績に関心があったためである。正善は、東京大学文学部宗教学科の卒業で国際的な宗教学者姉崎正治の下で研究を行い、宗教活動を行うのに文献的根拠が必要と考え世界中の宗教の教典や宗教書を集めることから始め、貴重な文献資料を集め始めた。そうして集められた蔵書が発展して天理図書館となった。彼は文献のみならず歴史、民俗、考古学関係の稀代のコレクターとして知られ、天理教が国際的な布教活動をしていた時期に各国支部から送られてきたコレクションは現在天理参考館と呼ばれる博物館で展示されている。
現在の天理図書館
函館図書館と天理図書館は古書店から古文献の出物があると競争するように購入し続けた図書館として、古書店業界では有名な存在だった。最近、この両図書館と関係がある第三の図書館があったことを知った。それが千葉県野田市の興風会図書館である。もともと野田醤油(現キッコーマン)系列の社会事業組織興風会が運営する私設図書館であった。これも現在は野田市立興風図書館となっているのだが、昨日、ここを訪問した。先の両館との関係というのは、かつてここの主任として活動した図書館員として仙田正雄(在職1941ー1943)と佐藤真(在職1943-1967)がいたことである。
この二人はがちがちの主張のある図書館員だった。仙田はもともと奈良の出身で天理図書館にもいたことがあった人だが、戦後に再度、天理図書館に入ってその後天理大学教授も務めた。興風会図書館で仙田の後を継いだ佐藤は、それ以前に函館図書館の職員で(在職1930-1943)、こちらに呼ばれてその後この地で長らく図書館長、郷土史家として活動した。
旧興風会図書館
筆者にとって仙田正雄は、戦前は関西の青年図書館員聯盟(一旦解散して、戦後は日本図書館研究会として再結成)の活動家で、アメリカ議会図書館東洋部でライブラリアンを務めたあと、戦争開始とともに帰国して関西で活動した人というイメージであったから、短いとは言え興風会図書館で働いたことがあったとは意外だった。仙田は資料組織論を中心に、図書館に関することについてさまざまなことに関心をもち発言をした人である。それは、彼の『楢の落葉』というエッセイ集によく現れている。また、記憶に残るのは、戦後の学校図書館導入期にいち早く文部省の『学校図書館の手引』の伝達講習会(1949)に手をあげ、率先して学校図書館制度を推進しようとしたことである。彼は分類や目録、件名目録が利用者あるいは学習者と資料とをつなぐ重要なツールであるという本質的なことを見抜いていた人だった。
「舌なめずりする図書館員」
佐藤については、「舌なめずりする図書館員」という言葉で記憶されている。これは「中小レポート」の関係者が『図書館雑誌』上の座談会で、郷土資料を扱う郷土史家的な図書館員が古文書を読む態度について、この皮肉な表現で批判していたのに対して、逆手にとって郷土資料こそが地域住民とのつながりを保持するための重要な契機になることを強調した意見であった。(太字は原文では上点がついている表記)
奉仕といっても、今日、明日生きている人々、または、生きるであろう人々に図書館資料を利用して頂くことと、将来(五〇年或は一〇〇年後も考えて)生まれてくるであろう人たちのことも考慮に入れながら、現在の図書館員が奉仕するということは、二通りの意味があると思う。そしてこの考え方は何時の時代の図書館員でも必ず堅持していなくてはならないものと私は考えている。特に、常に末端の民衆と深いつながりを持たなくてはならない中小図書館こそ、郷土資料を以上のような考えに立って集め、その職にある図書館員が、能力に応じて(勉強して)解読し、解説し、いい古された言葉であるが、”温故知新”の為に奉仕してあげるのだろうと考える。従って、その経過にあって、たまたまよろいびつの中の虫くい本(文書)があって、それを解き明かすことによって、地域住民の郷土に対する認識を改めさせ、今日の産業や生活姿勢を正すに役立つことがあるならば、舌なめずりしながら悦ぶのは当然すぎるほど当然なことではないだろうか。
筆者はかつて2度この文章の一部を参照したことがあるが、今回改めて長めに引用してみて前とは異なった感想をもった。岡田や仙田と同じ系譜の図書館員としての確固とした信念と、さらにそれを支える知識やスキルがあったことへの自負を感じる。
戦後図書館の隘路
人によっては、彼の考えは独りよがりのように聞こえるかもしれない。少なくとも、「中小レポート」(1963)、「市民の図書館」(1970)が「資料提供」の方針を打ち出したときに、図書館員は「市民」「住民」の要求という絶対的な存在に寄り添ってサービスをするべきであり、「奉仕してあげる」というような尊大な精神は捨てるべきだとした。公務員という枠のなかで仕事をしようとすれば、このような民衆を導くというような考えは成立せず、民衆の読書欲に賭けようと考えたのだ。これが有山崧と前川恒雄が先導した戦後公立図書館の論理である。それは的中し1970年代以降の大躍進があった。だが、それは高度成長とバブル経済という時代の好調な財政に依存して成立したものである。これが1990年代以降の公共経営論においては評価指標として突きつけられ、「来館者数」や「貸出数」にがんじがらめになって、四苦八苦する原因にもなった。自縄自縛に陥ったのである。
今挙げた三つの図書館はいずれも私設図書館としてスタートした。とくに興風会図書館長の佐藤は、東北帝国大学図書館から函館図書館に移った人で、戦後図書館の論理とは別の考えを保持していた人である。私設図書館、私立図書館は、日本の官の論理を強く意識するところから出発した「資料提供」とは別の図書館の論理を保持することができていた。私立函館図書館は1907年(明治40年)に設立され1928年(昭和3年)に市立図書館となり、2015年に指定管理制を導入した。天理図書館は一貫して天理教の聖地天理にあり、現在は天理大学付属図書館という位置付けであるが、一般への開放も行っている。興風図書館はずっと興風会図書館という図書館法上の私立図書館であったが、1979年に市に無償譲渡され、現在の市立興風図書館となった。
私設図書館が公立図書館と異なる論理があるとすれば、創設者の創設の理念が強力に働いていることである。図書館は営利事業にはなりにくいから、ある種の民衆奉仕の精神が働くし、その裏側には何かの訴えたい理念がある。函館図書館の場合は岡田の北方資料に対する強い関心があり、天理図書館の場合は布教活動に伴う真柱正善自らがもつ主知主義があり、興風会図書館の場合は醤油醸造業創業者のもつ社会奉仕精神と社会改良主義があった。目的が明確だからそれにふさわしいコレクションとそれにふさわしい手法があった。手法の重要な柱に目録や分類、書誌、などの資料組織活動があった。だからこれら三館には、資料のことがわかりそれを自在に操ることができる個性豊かな図書館員がいたのである。
公立図書館は「全体への奉仕者」としての図書館員が「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」(図書館法第2条)というような曖昧な目的を掲げざるをえないから、それを「資料提供」と言い換えることで無難な範囲でのサービスにとどまらざるをえなかった。そこでは、図書館員が本来もつ資料収集、組織化、排架、展示、レファレンスといったコレクション自体の価値を見極めて提供することができくくなった。1970年代以降、地方の時代が叫ばれ、一方で郷土資料、地域資料の重要性が言われていたにもかかわらず、コミットメントが浅くなったのはそれを意味する。せいぜいが、子ども読書とか障害者サービスのような国の政策に寄り添う部分でしか踏み込んだことができない状況となった。
おわりに
「舌なめずりする図書館員」は不要とされたのであるが、それで失ったものは資料についての専門知識と扱うためのスキル、そして図書館員としての気概ではなかっただろうか。少なくとも以上に挙げた三人にはそれらがあった。図書館員が全体としての奉仕者たらんとするためにも、それを裏打ちするものが必要である。とくに、MARCと図書館システムが導入されたことで、図書館員の専門性を発揮する局面が見えにくくなった。地域における図書館員の活動の源泉が地域におけるオリジナルな資料収集とその提供にあることは言うまでもないが、それをどのように提供するかが問題なのである。入ってきたものを分類し目録をとって書架に並べれば済むわけではない。市販資料なら、書店や広告や他の手段で存在が目につきやすいが、ローカルな資料はそうは行かないから、どのように見せるかが大事である。
函館と興風が公立図書館になってどのように変わったのか、あるいは変わらないのか。これが次の検討課題である。次に、興風図書館は現在でも興風会図書館時代の伝統が継承されていることを見ることにしたい。(続く)
<参考文献>
大石豊「興風会図書館の創設・発展と千秋社・興風会」『大倉山論集』第55輯, 2009, p.155-177.
川嶋斉「「興風会図書館」と「野田市立興風図書館」」『LRG』第28号, 2019, p.32-37.
坂本龍三『岡田健蔵伝ー北日本生んだ稀有の図書館人』講談社出版サービスセンター, 1998.
佐藤真「舌なめずりする図書館員」『図書館雑誌』 58巻7号, 1964年6月, p.304-305.
丹羽秀人「岡田健蔵と市立函館図書館」『LRG』第28号, 2019, p.60-65.
根本彰「戦後公共図書館と地域資料—その歴史的素描」日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員会編『情報公開制度と図書館の自由』日本図書館協会, 1987, p.62-93.
根本彰「地域資料・情報論―図書館でどう扱うか」『図書館雑誌』 95巻12号, 2001年12月, p.922-924.
浜田泰三 (編)『やまとのふみくら―天理図書館』中央公論社, 1994, (中公文庫).
*昨日、千葉県立図書館の大石豊さんにお会いし、上記の論文をいただいた。この論文に目を通したとき、三つの図書館が私のなかでつながった。ヒントを与えてくださった大石さんに感謝したい。