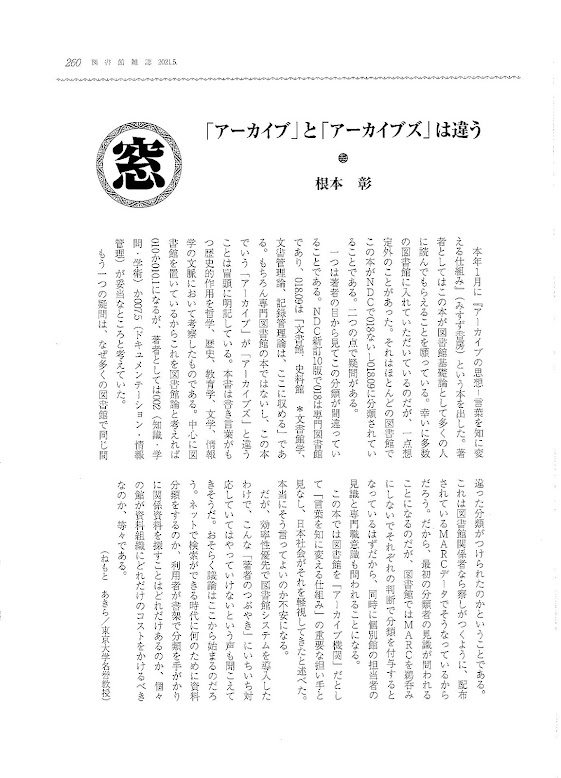オンライン資料の納本制度についての私論
前項に続いて、このオンライン資料やデジタル資料の利用についていささかの私見を述べておく。関連の論考として、根本彰「知識資源のナショナルな組織化」(根本彰・齋藤泰則編『レファレンスサービスの射程と展開』日本図書館協会, 2020, p134-162)があるので併せて参照されたい。なお、オンライン資料以外の、従来の納本制度の対象資料と対応するデジタル資料の納本制度の必要性については最後に述べておきたい。
NDLのデジタル化戦略
デジタル資料を梃子にしてNDLの現代化を図るというのは、かつて2007年から2012年にNDL館長を務めた長尾真氏が取り組んだものである。長尾氏の館長時代にNDLは資料のデジタル化、納本資料に電子出版物やオンライン資料を含めること、そしてインターネット資料の自動収集制度を始めた。これらは従来の図書館が対象とする資料の範囲をデジタル資料の方向に大幅に拡張することになっただけでない。国立国会図書館法改正だけでなく著作権法の改正も行っているように、官庁、自治体、出版社、著作者を巻き込んだかなり大きな制度改革である。
まずインターネット資料の自動収集であるWARPは国および地方自治体の機関のみ対象だが、ネット上で発信した政府情報や自治体情報を定期的にアーカイブ化を行って蓄積するものであり、こうした情報の保存・公開という意味できわめて重要である。そしてオンライン資料という新しい概念を用いた納本制度というのは、たぶん苦心のアイディアなのだと思われるが、ネット上のデジタル資料で従来の図書館資料のイメージにもっとも近い図書と逐次刊行物形式のものを納本対象にしたということだ。これが重要なのは、民間の出版社にとって紙からデジタルへの移行における試金石になるということだ。
というのは、従来紙の図書は刊行したものの1部をNDLに納本するのは取次が代行しており、あまり気にかけずに済んでいた。納本制度が始まったばかりの頃には戦前の検閲制度の記憶も濃厚にありさまざまな抵抗があったものだが、今のような仕組みになって安定的に運用されていた。が、今回、有償オンライン資料の納入が義務化されることで、電子書籍や電子雑誌の納本について改めて一からすべてを議論しなければならないだろう。その際に、改めて納本制度とは何なのか、国はなぜ民間が出版した資料の納入を義務づけているのか、さらには納入した資料はNDLでどのように利用されるのか、次に述べる長尾氏の構想とどのような関係になるのかなどについて問われるはずである。
長尾構想とは何か
長尾氏は、館長就任後間もない2008年に私案として「電子出版物流通センター」構想を発表した。それは次の図のようなもので、ここには少々修正したかたちで2015年に再度提示されたものを掲げている。出版社から納本された出版物をNDLがデジタルのまま受け取り「デジタルアーカイブ」に置かれる。カッコ付きの納本制度としてあるのはまだ法制度が整っていないからである。紙のものはデジタル化されて「デジタルアーカイブ」に納められる。これは館内の利用者が利用できるし、公共図書館等を通じて館外の利用者にも利用できるようになる。また、デジタルアーカイブから新たにつくられる「電子出版物流通センター」にデータが「無料貸し出し」されて、ここが「販売」「有償貸し出し」「権利者へのアクセス料金の配分」の業務を行うことになる。要するに、NDLの外側にできる電子出版物流通の拠点が納本制度によって集められた電子出版物をもとにビジネスを行う拠点になるということである。

長尾真「知識情報の活用と著作権」『デジタル時代の知識創造』角川学芸出版 2015 p30 より
立法府に所属する一見すると地味な図書館がこのようなデジタルコンテンツの収集・提供を行うという発想が型破りでありインパクトはあった。だがこれは館長の私的な構想であって、実際にこの図のように事が進展したわけではない。
まず、オンライン資料の納本制度についてはようやく今回の制度改革でカバーされるようになった。この図の左側の国立国会図書館の部分については構想後13年目にして実現されようとしていると言える。また、(1)で述べたように著作権法改正の議論が進んでいて、デジタル資料の国民への無料での直接送信や公共図書館等を経由しての提供はこの図が示すもの以上に進展することになる。他方、「電子出版物流通センター(仮称)」はつくられなかったし、今後もつくられる様子はない。
長尾構想は、日本で電子書籍や電子雑誌の発行が遅れているからNDLが率先して納本制度を梃子にして国民への安価な提供システムをつくろうという趣旨で提案されたものである。だが、電子書籍市場は今でもコミック中心であり、あとは紙で刊行されたものが少し遅れて電子書籍化されて市場に登場しているが、それは紙の出版物の一部である。電子書籍市場において、納本制度はこれまでは無償でDRMなしの出版物のみが対象であったから目立ったものとはなっていない。また、紙のものはNDLに直接納本されるのではなくて、取次が代行しているから、官主導で流通を促進するという議論が出版関係者にピンとこなかっただろう。
雑誌は学術雑誌は確実に電子雑誌化しているが、それ以外の商業的分野では紙ベースの雑誌市場は縮小されつつある。休刊になった雑誌記事の一部は新聞社や出版社のサイトからのオンライン記事として発信されたり、新書版の書籍として出版されたりしている。図書も雑誌もまだ成熟した電子出版物市場はつくられていない。遅れた理由ははっきりはしないが、コミック以外の電子書籍の市場形成が十分ではないことを意味するのだろう。そこには、図書館での利用を前提とした法人市場がうまくつくれていないことも含まれる。
民間オンライン資料の納本制度の成否
出版関係者には電子書籍や電子雑誌の納本制度について、すでに一定のイメージができあがっているように見える。それは電子出版物の納本はやっかいだということである。というのは、紙のものなら1部納本してそれがNDL内で利用されてもあまり販売に影響がない。むしろ確実に保存してくれるというメリットがある。しかし、電子的なものは納本されればそれが容易に外部に発信可能になる。デジタル出版物は所有権、著作権にもましてそれをどのように使うかのコントロール権が重要なのだが、DRMをはずすということはそれを他者に与えることに等しいから問題になる。
しかしながら、オンライン資料の館外送信についてはまず著作権上の問題がある。外部送信のためには著作権が切れているものが対象でなおかつ絶版になったものしかできない。ここにTPP協定により著作権法が改正され、保護期間はかつて著作者が亡くなってから50年だったものが2018年末から70年に変更になった。これにより、NDL所蔵のデジタル資料の著作権は1968年までに亡くなった著作者のものについてはフリーになったが、1969年から1989年までに死去した著作者の著作については50年差の2019年以降にフリーになるのではなくて、70年後の2039年以降に1969年から順に1年ごとに繰り下がってフリーになっていくことになる。つまり、著作権法で保護される期間が20年間延長されたことの影響は大きい。このことを出版社やベンダーは十分に理解していないのではないか。(*下線部は最初の稿で間違っていたので修正した。2021/05/06)
次に電子書籍への移行により、「絶版」という概念がなくなりつつあることも指摘しなければならない。かつてなら印刷された部数が売れて在庫がなくなった段階で増刷しなければ絶版とされたが、それでもどれが絶版なのかは曖昧だった。ところが電子書籍はデータがあればいつでも販売可能だから絶版という状態はないことになる。だから電子書籍化され販売されている限り、それがNDLから無料でインターネット上で利用可能になることはありえないことになる。
以上のことから、著作権保護期間延長があり、電子書籍化によって絶版がない状況がつくられるとオンライン資料として納本されたものも外部送信しにくくなり、出版社や著作者にとっては不都合な状況を避けることができることになる。紙の本のように取次一括で納本されるのでないから、出版社や著作者の心配ないし誤解をていねいに解かなければなかなか納本は進まないだろう。このあたりについて、報告書は、金銭的補償にこだわらず、政策的補償に相当するインセンティブが必要であるとか、著作の真正性の証明、データバックアップ機能、統合的検索サービスから本文情報へのナビゲートがインセンティブとして期待されるというように、納本することが著者や出版社にとって著作物の文化的な保全をもたらすものであることを述べている。このあたりも含めてオンライン資料の納本の重要性をどの程度説得的に示せるかにかかっている。
オンライン資料以外のネット上デジタル資料
最初に述べたように、納本制度は伝統的な9種類の資料を対象としていた。再度示すと、
一 図書
二 小冊子
三 逐次刊行物
四 楽譜
五 地図
六 映画フィルム
七 前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八 蓄音機用レコード
九 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物
である。今回の改定で1の図書と3の逐次刊行物に相当するオンライン資料が納本の対象となることになったが、それ以外のものでデジタル化されてネット上にあるものは対象にならないのかという問題が残されている。2の小冊子と7の複製した文書又は図画というのは曖昧な概念で、ひとまず図書と逐次刊行物に含まれると考えてよいだろう。しかし、それ以外の楽譜と地図は別の資料であり、それらのデジタル版は多様な展開を示していると考えられる。また、6の映画フィルムと8の蓄音機用レコードのデジタル版は9に含まれることになる。総じて、9に該当しインターネット上でアクセス可能になっているものをどう扱うかという問題である。おそらく9の概念をつくったときに、それがネットワーク上に置かれているものについてどう扱うかという問題意識はあったものと思われるが、今回までの改定ではそれについては触れてこなかった。
この問題については、最初からこれをNDL一館でやることは難しいのではないかと考える。たとえば、6の映画フィルムについては、国立国会図書館法の附則で納入を免ずるとあってNDLは納入機関になっていない。実質的には東京国立近代美術館国立映画アーカイブ(旧名:フィルムセンター)が1970年に開設されて以来こちらが、映画資料の保存機関であった。(
http://archive.momat.go.jp/FC/filmbunka/index.html)つまり図書や逐次刊行物は図書館が扱うのに適するが、それ以外のマルチメディア資料についてはNDLが納本図書館という原則そのものに無理があったというのは早い時期から知られていたのである。
ちょうど昨年の8月からジャパンサーチが本格稼働していて、これは国や大学等の博物館、資料館、公文書館、資料館、図書館の資料(現物、デジタルアーカイブ)の横断的サーチを行うものである。ここには国立映画アーカイブも含まれている。オンライン資料の納本についても、「リポジトリ」で扱えるものはそちらに委ねるという方針が採用されている。これを延長すれば、マルチメディア資料およびそのデジタルアーカイブについてはそれぞれの専門機関が扱い、NDLは印刷物を原形とするものを対象とするというような切り分けによる分担の制度が必要になっているように思われる。
最後に、残された問題として、ネット上のコンテンツの納本制度をどう考えるかがある。映画の法的納本制度が免除されていたわけだが、マルチメディアの各種資料について改めて納本制度をつくることが可能なのか、あるいはそれは必要なのかということである。複数機関での分担アーカイブを前提とするとすでにそれは難しくなっているように思われる。