【最近読んだ本】*執筆・研究活動以外でここ1年くらいで読んだ本を挙げて一言感想を書いておく。今年も『みすず』1/2月合併号に寄稿したが、そこに納められなかったものを中心にしている。なお、このみすず書房のPR誌は今年の8月号で休刊となり、「WEBみすず」(仮称)になるそうだ。いよいよ紙からデジタルへの動きが急にも見えるが、他方、人文書では紙版を重視することは変わっていない。以下で文献学(Philologie)関係を意識しているのはそれと関わっている。『みすず』1/2月合併の「読書アンケート特集」は今後も残すそうである。
竹田青嗣『ニーチェ入門』筑摩書房, 1994.(ちくま新書)

竹田氏が先行思想家の考えを咀嚼して自らの言葉で分かりやすく表現してくれることは、この30年近く前の著作から一貫しているということを改めて知った。ニーチェは敬遠してきた思想家だったが、この本を読んで考えが変わった。言葉の力によって、人文主義、文献学の系譜が21世紀まで生き延び、さらに展開しつつある意味を確認させられる。
堤未果『デジタル・ファシズム:日本の資産と主権が消える』NHK出版, 2021.(NHK出版新書)

「○○DX」が何を意味するのかを率直に語った本。とくに「第Ⅲ部 教育が狙われる」に惹かれて読み始めたが、読んでいるうちにこの本が「NHK出版」から出ていることの意味についても考えさせられた。放送(broadcating)という特権的なメディアをもち、さらに受信料獲得が放送法で保証された「公共放送」であるNHKがグローバルなデジタルネットワーク社会の到来で今後どうなるのか、強い関心をもっているはずだからである。情報インフラの利権をめぐる闘いにこの本も置かれている。
小坂井敏晶『格差という虚構』筑摩書房, 2021.(ちくま新書)

フランス在住の論客の格差論。彼の地にいるからこそ見えることがあり言えることがある。人間が一人一人遺伝的にも、生育環境でも、社会環境でも違いがある以上、格差があることは当たり前である。だが、すべての人が現実社会に生きるために、制度的にどのように対応するのか、そのときの規範や方法はいかにあるべきなのか。
ブランコ・ミラノヴィッチ(西川美樹訳)『資本主義だけ残った:世界を制するシステムの未来』みすず書房, 2021.

タイトル通り、グローバル資本主義を分析した本。その意味では当たり前のことを論じているが、それがきわめて実証的でかつ重厚に論じられていて説得力がある。リベラル能力資本主義(米国)vs. 政治的資本主義(中国)に対して前者を一方的に評価することをせずに冷静に見ようとするする態度は、著者が東欧出身で世界銀行でエコノミストをしていた人だからか。
木庭顕『クリティック再建のために』講談社, 2022. (講談社選書メチエ)

今回挙げた本ではこれが一番の難物で、何度か読み返し、読書会参加の人たちとの議論を経てようやく著者が言おうとしていることは把握できてきた。Amazonの読者評にもあるが、この本は「メチエ」シリーズの他の本の構えとまったく異なって、著者が展開してきた古代ギリシア以来の言語哲学とローマ法以来の法哲学をベースにして書かれた思想史をつなぎ合わせたものである。じゃ、元に戻って以前の著書(『政治の成立』以下の三部作+『人文主義の系譜: 方法の探究』)に当たれば理解しやすいかといえば確かにそうだが、それぞれを消化するにはかなりの知的努力が必要だ。日本の人文社会科学の極北に位置する著者の業績はたぶん半世紀くらいしないと理解されないのだろう。
佐藤彰一『歴史探究のヨーロッパ:修道制を駆逐する啓蒙主義』中央公論社, 2019.(中公新書)
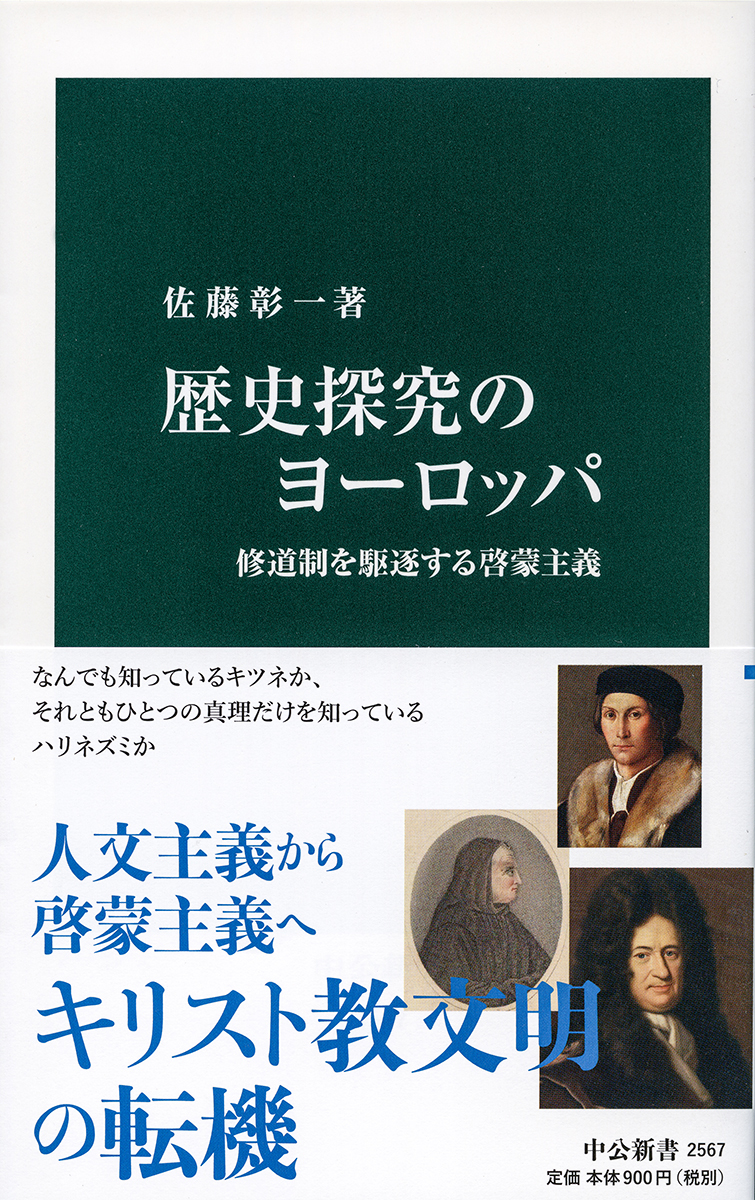
上記の木庭氏の本でも触れられている。この本は著者がヨーロッパの中世から近世への転換期をテーマとする歴史学のシリーズの一冊で、「修道制」が前面に出ているけれども、テーマとしては、人文主義(フマニタス)、文献学(ビブリオロジー)とは何かを中心的に論じている。近代の実証主義的歴史学においては、サンモール修道会のマビヨンらによって、伝わる文書や写本の真正性を明らかにする方法が確立された。だが18世紀になると啓蒙主義の台頭でフマニタスやビブリオロジーの位置付けが見えなくなっていく。
エドワード・W・サイード(村山敏勝・三宅敦子訳)『人文学と批評の使命:デモクラシーのために』岩波書店, 2013.(岩波現代文庫)

文献学は死に絶えていないどころかデジタルヒューマニティーズによって新しい展望が与えられつつある。サイードは『オリエンタリズム』で知られるパレスチナ出身の論客であるが、この本では19世紀ゲルマンそしてフリードリッヒ・ニーチェを経由してアウエルバッハなどの20世紀の人文学につながり、そしてさらに新たな展開を示唆している。バルト、フーコーやデリダなどのアンチヒューマニスティックな人文学も文献学をルーツにしていることも述べている。
坂本尚志『バカロレア幸福論』星海社, 2021.(星海社新書)

フランスの高校卒業資格のための試験制度バカロレアで哲学が課されることは知られているが、近年、著者らの研究によってその内実が明らかにされてきた。哲学をやると幸せになれるというのがどれだけ当てはまるのか。上の小坂井氏や木庭氏の議論などを見ていると疑問もある。同じ著者の『バカロレアの哲学:「思考の型」で自ら考え、書く』(日本実業出版社, 2022).も合わせて読み、少なくとも自分の考えを表現する方法として有効ととらえる。


