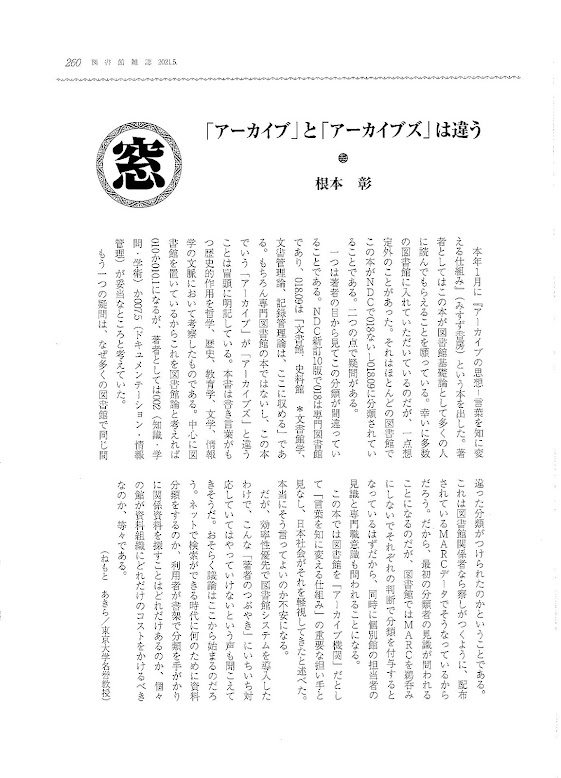根本彰『アーカイブの思想——言葉を知に変える仕組み』(みすず書房, 2021)に対する書評(2)の続きです。
書評者:中野目徹氏『日本史学集録』(筑波大学日本史談話会) 42号, 2021年7月, p.49-52. (アクセスはこちら)
【謝辞】この雑誌は筑波大学関係者を中心とした研究会の雑誌であるが、オープンジャーナルとなっていないのでなかなかアクセスしにくい。そこで評者の許諾を得てこのブログで読めるようにした。掲載を許可していただいた評者に御礼申し上げる。
はじめに
中野目氏は筑波大学で近代日本思想史を担当している歴史学者である。この書評の最初に出てくるように、2020年3月に私が慶應義塾大学を退職するにあたって最終講義を兼ねた公開シンポジウムを予定していて、そのときに招待してお話しを伺おうとした方である。そのイベントはコロナ禍で中止になった。どういうイベントが予定されていたかに関心があればここを見ていただきたい。拙著自体がそのときの最終講義で予定していた内容を大きく展開したものであったが、氏の書評もまたそのイベントでお話しになる予定であったところから出発しているということだ。このような形でお返しいただいたことに感謝申し上げたい。
実は氏と20年前からの因縁があったことは、この書評の後半に、拙著『文献世界の構造——書誌コントロール論序説』(勁草書房, 1999)で述べたことが北海道文書館職員(当時)青山英幸氏の著書『記録から記録史料へ——アーカイバル・コントロール論序説』(岩田書院, 2002)で方法として用いられ、青山氏の著書の書評を中野目氏が書いていたとあることから分かる。書誌コントロールとアーカイバル・コントロールとの関係は図書館の方法と文書館の方法の関係に相当する。私自身は青山氏から同書をいただいていたが、あまりそのことを考察しようとしていなかった。改めて考えてみると20年越しで『アーカイブの思想』を書いたことの遠因に両者の関係の重要性に気づかされたことがあったのかもしれない。今なら、もう少し知識組織化の方法の議論に踏み込むところなのだろうが、今回は少し触れただけであり今後の課題の一つとなる。
以上のことは措いても、中野目氏は思想史学者であるが筑波大学に赴任する前に国立公文書館にいらして『近代史料学の射程』の著書もあるように、公文書や公文書館について詳しいし、現在でも筑波大学文書館の責任者を務めている。つまり、私が図書館の専門家であるとすればアーカイブズの専門家でもある。だから本書が「アーカイブ」を名乗りながら実は「アーカイブズ」についての記述が弱いことはすぐに見抜いただろう。ただ、そのことはおくびにも出さず、本書をintellectual historyの視点から読んでくれたという言う。これはたいへんありがたい。
私にとって思想や歴史という領域は今でこそ身近となったが、かつては遠い領域であった。1970年代前半に文系の大学に入ったものとして、錚々たる人たちが侃々諤々の議論をしている思想や歴史の壁はたいへん高く厚く思え、まったく違ったアプローチをとることを選択した。そういう自分が半世紀してそうした領域に近づくことは冒険でもあった。本書で何度か言及したように、西洋の人文知の成り立ちを意識する見方を日本の人文社会科学の領域にぶつけてみることこそが、下手の横好きとか大風呂敷とか言われようとも、本書の独自性であり、それを正面から読み取ろうとしてくれたということがうれしいものであった。
アーカイブとドキュメントの違い
書評では本書の構成に沿って全体を紹介した上で、最後に3点の著者に「教示願いたい点」を指摘している。これに答えるのが著者の務めであるだろう。以下、襟を正して批評への応答を試みたい。
まず、本書の冒頭で「アーカイブ」と「ドキュメント」を定義しその違いと関係について述べている。評者はこれが「アーカイブズ(文書館)と図書館(さらにアーカイブズ学と図書館学)の関係にほかならないが、両者の位置関係が不明瞭であり、本書の主題と対象の不明瞭さにつながっている」と感じられたとしている。とりわけ、日本の近代化を論じた第9講について、「今後より一層検討を加えていく必要がある」と述べている。第9講が近代思想史家の眼からするとずさんな議論にも見えるだろうとは予測できることである。この分野について、日本史学なり近代思想史学なりの蓄積がすでに大量にあり、それからつまみ食い的に取り出して論じているようにも見えるだろうからである。だから、問われるべきは、そのつまみ食い的取り上げ方の正当性を主張するための方法的根拠である。そして評者は、著者がそれをアーカイブとドキュメントの違いを基に展開していると読んだのであろう。
本書の立場を言い換えると、「アーカイブ」とは起源へと回帰するベクトルであり、「ドキュメント」とは逆に未来へ向けて拡散するベクトルであるということになる。アーカイブと歴史、ドキュメントと知を対応させているのはそのためである。歴史学は現在を構成するものの最初がどうであったのかを問い、それを明らかにするのがアーカイブズ(オリジナルな文書や記録類)であるとする。他方、それ以外の人文社会系の学問は本書の立場から言えば起源後の現象の展開についての知である。知を獲得する方法はそれぞれの学問毎にあるが、それで構成された知はいずれも仮説にすぎない。そして、知は自らの支持者を増やすために拡散の方向で展開する。書物、論文、ネットいずれもがコピーであり拡散のためのツールである。実は歴史学の問いも現在を説明するために行うものであり、起源を問いながらなおかつその解釈を行うという意味で他の人文社会諸科学と変わりはない。つまり、歴史学もそれ以外の人文社会科学もいずれもアーカイブ、ドキュメント両方のベクトルをもちながら、自らを形成してきたと考えるべきなのだろう。
極論すれば、アーカイブはオリジナル、ドキュメントはコピーを志向するが、その関係は相対的にしか決まらないということになる。文書館と図書館の関係もここから導かれる。一点しかない文書、その写本、版本、影印本、文書を集めて編纂して活字化した資料集、この文書を解説した書物があるとして、文書館はどれを集めてコレクションにするのか、図書館はどうか。どこまでがアーカイブズでどこからがドキュメントか。それは一律には決まらないが、しかしながら論理は明快である。
あらゆる学問において先行研究の確認が行われる。たとえば理系の研究で先行研究と言えば、当該領域の最新の研究成果である。だが、研究史を遡ってその研究を手掛けた最初の論文にはすでに研究上の価値はなくなっている。とはいえ、STAP細胞事件のようにひとたびその研究がフェイクの疑いがかけられたとき、たちまち当初の論文は研究史的な意味でのアーカイブとなり検証の対象になる。このことを逆に言えば、理系の研究論文は最初の論文が査読を通り公表された段階でアーカイブの段階からドキュメントの段階になり拡散の道をたどるということである。そして通常、アーカイブを問題にすることはない。アーカイブの真正性がドキュメント拡散のプロセスに埋もれているからである。ただし、この場合でもアーカイブは常に検証の対象として存在している。
このように、アーカイブはいずれドキュメントに変わる。そのタイミングが自然科学と人文社会科学では異なっているということである。また、ドキュメントの分析自体を行う文学や哲学などの領域はドキュメントをアーカイブととらえているとも言える。たとえばゲーテでもルソーでも福澤諭吉でもいいが、文学や思想研究者がいちいち著者のオリジナルの原稿を読みにアーカイブズに行くことはないと言ってよい。原稿のファクシミリ版のようなようなものを読む場合、刊本になった全集本を読む場合、さらにはその翻訳の文庫本を読む場合でも、それはアーカイブを読んでいるわけである。それは書誌学的な校訂を受けて原典と同一である、あるいは原典にもっとも近いものとして読んでいる。翻訳ですら、原典を忠実に訳したものとして扱われる。これらもドキュメントであると同時にそういう手続きを経てアーカイブが埋め込まれていると考えられる。
中野目氏の疑問に戻ると、だから両者の関係が曖昧に見えるのは仕方がない。さらに、両者の原理的な違いと相互関係は文書館や図書館の制度的違いとは対応しにくいところもでてくる。たとえば、内閣文庫(現国立公文書館)のようにドキュメントをもつアーカイブズがあったり、憲政資料室のようなアーカイブズを国立国会図書館が部門としてもったりすることがあるわけである。両者の関係は、戦後改革でGHQ/SCAPが図書館を重視したことによって、一時的に図書館が制度化されたことにより、関係者が国立国会図書館を文書館として用いたことにある。だが、同館のモデルになったアメリカ議会図書館(LC)は近くに国立公文書館(NA)があるのに、アーカイブズのセクションをもち大量の資料を集めて公開しているから、別に日本の特殊事情とは言えないだろう。公文書館法、公文書管理法以降の日本では、公文書館を発展させている状態で図書館や博物館などにあったアーカイブズを改めて文書館に移管することも進行している。ようやくアーカイブズが公文書館で扱われるような事態が生まれつつある。
東洋の書物と文庫
次に、本書が欧米の人文学的なコンテクストのなかで図書館のことを語り、中国や日本の書物や文庫などの知の系譜との関係の整理が十分ではないとの点である。本書では第8講まで西洋の知の系譜について述べて、第9講で日本の対応するものがどうなのかという議論をしている。江戸期の書物とその蓄積および流通と知識人の交流について少し述べ、また幕末には会読のような西洋で行われていた知の交流と深化させる方法があったことについても述べている。しかしながら、それが明治政府が本格的に稼働するにつれて、国力を強化することが目標になり、知の領域も蓄積しながら自由な交流を前提にするのではなくて、知を輸入して翻訳して配布するようなものが中心であったと述べている。内部に蓄積しつつ新しい知を創造するのではなく、外部からの翻訳学問が中心になっていくことや、国民自体を国力と位置付ける観点から、学校教育における知および倫理の在り方を国家が統制していったことについて批判的な議論を行った。
評者はもとより日本思想史の研究者として、それでは江戸期までの知の蓄積との関係がよく見えないという批判をお持ちなのだと思う。本書でも国学的伝統が天皇制国家の知的倫理的水準を決定づけたことについては言及しているが、氏が指摘している、明治のジャーナリスト徳富蘇峰の成簣堂文庫に和漢洋の資料の蓄積があることで分かるように、明治の知識人が決して漢学や国学の伝統だけではなく、中国、仏教、洋学のさまざまな知を吸収しながら議論していったことは確かだろう。明治初期の啓蒙主義者のなかで天皇制の推進者になった人が少なくないことは確かであるが、このあたりの事情を十分に把握して論じることはできていない。また、中国や日本の文庫的伝統や類書、考証、類聚、編纂物といった「書物のアーカイブ戦略」(本書p223以降)についての考察や日本の教養主義と修養主義の関係、そして出版と知の流通の考察(p246以降)はあるが、全体としてきちんと検討が進めらることはできていない。それは西洋の知の系譜を基準にして日本のことを議論したことによる限界であることは自覚している。
ただ、一点言い訳のように付け加えておけば、西洋の知的伝統の在り方とアーカイブの思想が近しいものであり、それが図書館や文書館といった制度面に現れていることを強調したかったことは確かである。これは、図書館情報学という分野が制度としての図書館が十分に展開しないと成り立たないという弱点をもっていることと関わっている。近代日本の書物の問題は私自身の課題であると同時にこの時代のさまざまな領域の研究者が進めてくれているので今後ともいっしょに考えていきたいことである。
デジタルアーカイブについて
多くの記録物がボーンデジタルで発生し、すぐにネットで使用可能になる状況についても十分に議論していない。また、評者があえて「デジタルアーカイブズ」と表記された文書・記録史料類のデジタル化についても本書では述べていない。私自身は入っていないがデジタルアーカイブ学会の活動もあり、近しいけれども遠巻きに眺めているという感じである。というのは、これは今のデジタル庁創設の動きとも密接にからむもので、国のICT対策が出遅れているという危機感を先取りしてデジタルコンテンツの創出を目指すが、やはりそうした時流に乗った動きとも見えるからである。時流に乗ることもときには重要でむしろ図書館の領域は乗るのに失敗してきた歴史とも言えないことはない。ただ、どうも気質的にそういうものから離れたがるところがある。
もう少しこれまで述べてきたことの延長上で議論すれば、デジタルアーカイブはアーカイブといいながらドキュメントの拡散をデジタルネットワークの上で目指す手法である。確かに一点しかないアーカイブズがどこにいても画面上で見ることができるというメリットがあることは何にもまして否定できない。これは図書館の領域でも同様で、国立国会図書館のデジタルコレクションがネット上で公開されたことで人文社会系の研究者が今まで知らなかった、あるいは入手できなかった古い資料に容易にアクセスできるようになったことを歓迎する声をいろんなところで耳にする。だから、日本の貧弱なアーカイブ環境を改善する重要な手法であることは間違いない。これに、ジャパンサーチの横断検索の機能によって個別の機関がつくるデジタルコンテンツへのアクセスがさらに容易になることが拍車を掛けている。
だが、物事には両面があるもので、この手法がアーカイブと名付けられ、これによってアーカイブ問題が解決すると考える人が出てくるとしたらそれは大きな問題だろう。これはアーカイブズ関係者には自明のことだが、デジタルアーカイブの素はあくまでもすでにある紙ないしはパッケージ系のメディアであり、過去存在していたが消失したり行方不明になっものを掘り出してアーカイブ化することではないし、また、これによって、公文書の移管手続きが進んだり、ボーンデジタルの公文書類が保存されるようになることでもない。つまり制度として問題になっている公文書の保存公開や公文書館への移管問題とは直接関係ないのだが、そうした問題が存在することの目くらましの効果もあることに不安を覚えているということである。
言い換えれば、私が考えるアーカイブズの世界においては、アーカイブズの存在を認識しそれを意識的に残すことから始まり、あとは組織的に保存し、必要に応じて公文書館に移して組織化して利用可能にするところまでを含むのだが、デジタルアーカイブはその最後の部分にはきわめて有効だが他の部分には影響がないということである。全体としてバランスのよい展開を考える必要があると思う。
おわりに
思いがけず真摯な書評をいただいたので、余計なことを含めて書きすぎてしまったかもしれない。本書のなかで大元の図書館情報学に当たる部分は全体のごく一部で、中心は歴史学、哲学・思想史、教育史・教育哲学、文学史・文学理論などに拡がっている。自分にとって他分野の方からのレスポンスをいただくことも経験した。また、そうした交流によって新しい分野が開けていることも分かってきた。21世紀も20年がすぎて本格的な新世紀の相貌が現れつつある昨今であるが、知の状況を俯瞰的に見る方法論を探るのが楽しいという実感はある。