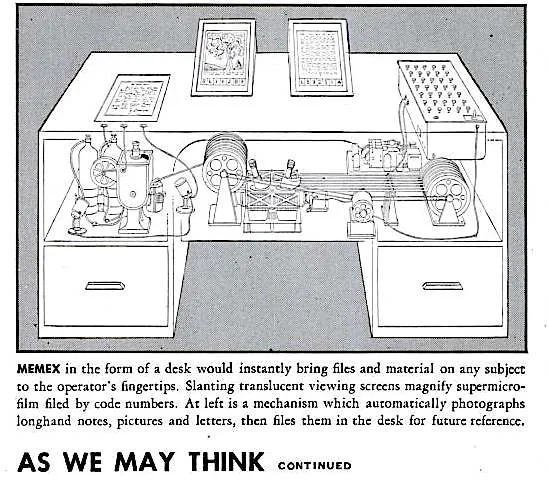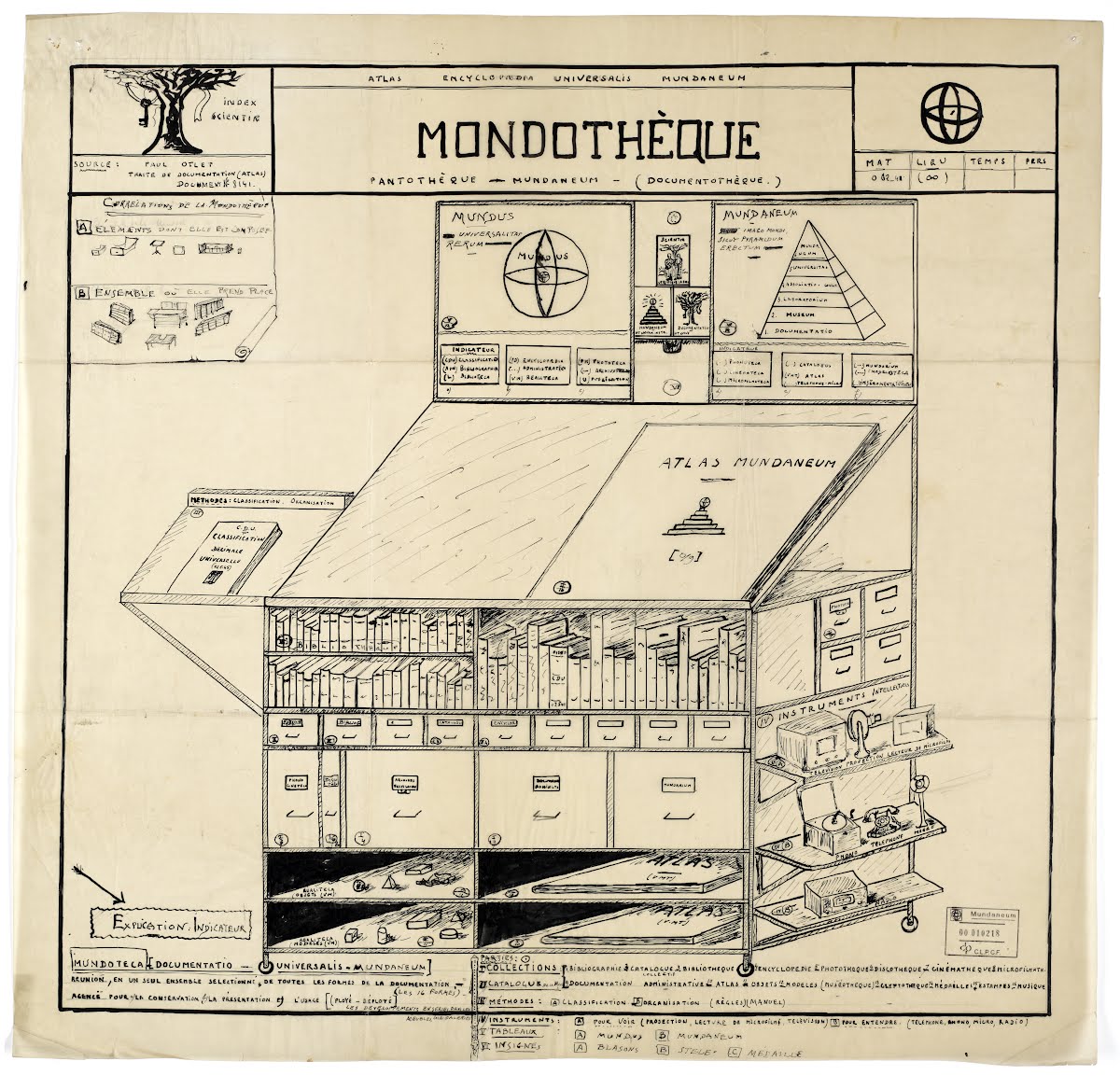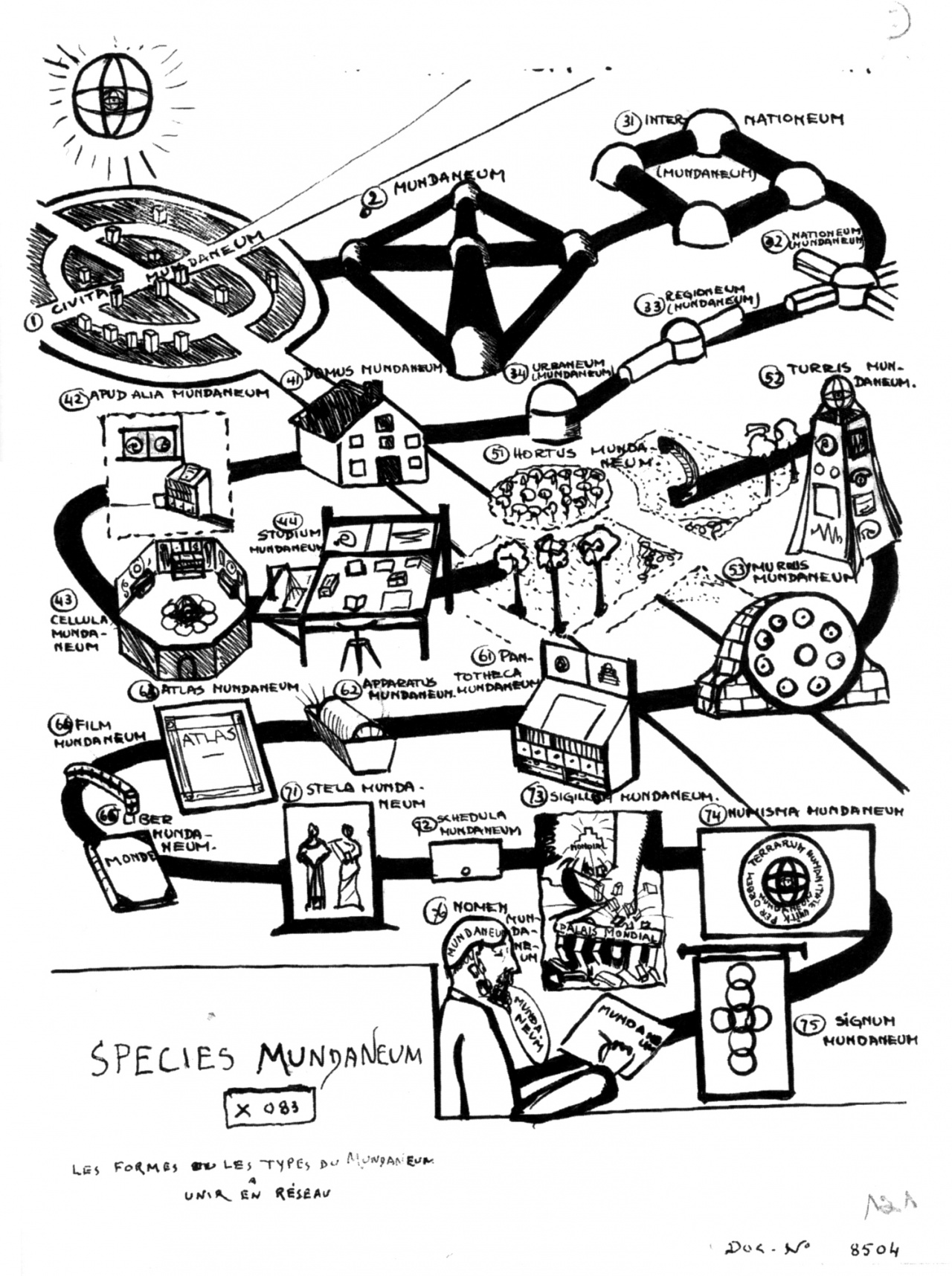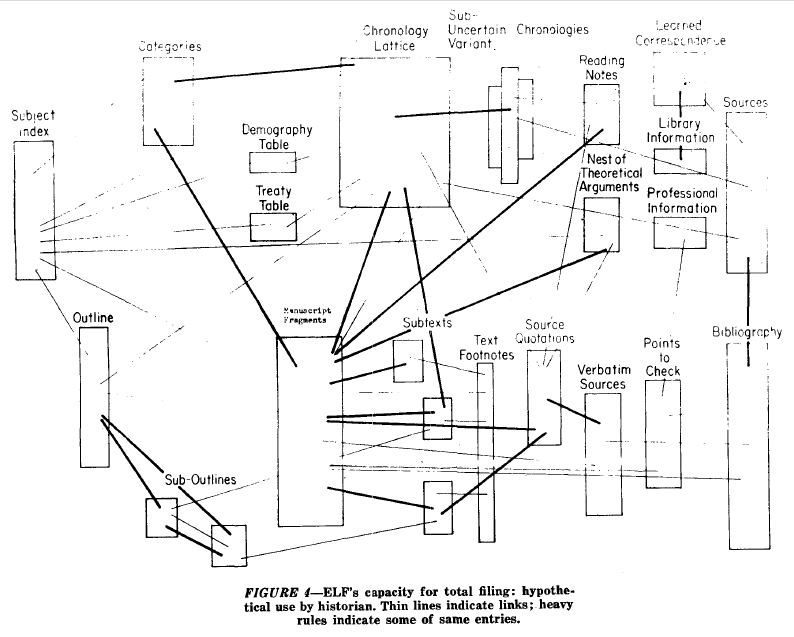地域アーカイブ研究を始めたときから,北海道の町立図書館を対象にすることは決めていた。ナショナル・アーカイブと地域アーカイブの思想史的な問題は別に論じることにして,ここでは,地域アーカイブとは当該地域のアイデンティティ形成において一定の役割を果たす機関やメディアなどの仕組みないしその作用と大雑把に定義しておく。ここにはひろくみれば,自治体の役所や商工会,学校,地域メディア,出版,図書館,博物館・資料館,文書館などから,今なら,SNSやブログ,動画プラットフォームなどまでも含むことになる。
とくに図書館活動の観点からは,次の4つのポイントを抑えておく必要がある。もっとも基本的な「地域資料・郷土資料の収集・保存・提供」はもちろん,「自治体行政との関係」は図書館とその行財政上の基盤であることと行政に対するシンクタンク機能を提供するものと考えられる。さらにアーカイブ機能の柱となる「自治体史編纂,歴史資料保存との関係」,そして図書館と並んでアーカイブ機能を果たす「博物館・美術館・公民館活動との関係」といった項目を見ておく必要がある。
また,北海道をなぜ選択するのかについては,すでに,昨年の日高地域の町立図書館訪問の報告で書いておいたのでそちらを参照していただきたい。そのなかでも置戸町立図書館について少しだけ触れているが,これまでも何度か北海道を訪ねてたまたま通りかかった町の図書館をいくつか見て上記の地域アーカイブ活動という意味で優れているところが多いと感じた。それなら,北海道町立図書館が注目される原点とも言うべき置戸町がどうなっているのかをみたいと感じた。
置戸町の概要
置戸という町の概要を見ておくと,北海道北東部の町で,北見市からはオホーツク海と反対の山側に車で30分ほど進むと到着する。すでに廃線になった旧国鉄網走本線(池北線)が開通した1910年代から開発が進み,徐々に人口が増え,戦後間もない1955年頃には林業や木材加工業で賑わっていた。当時、1万2千人ほどあった人口は現在では2700人あまりで,典型的な過疎の町ということができる。主産業であった林業,林産工業がエゾマツ,トドマツの原生林の伐採や台風による風倒木による原価高騰,安価な輸入材の増加等で成り立たなくなっていったことが大きい。現在は畑作の農業や乳牛の牧畜業が主たる産業である。
次に,置戸の中心市街の地図を見ていただきたい。赤で囲んだ施設が図書館である。東西に流れる川の北側にできた中心市街は,コミュニティホール(旧JR置戸駅)を真ん中にして南北に二分される。これはかつてJR池北線が町を通っていたからである。北側は商業生活エリアでスーパーやガソリンスタンド,病院,郵便局,町役場などがある。これに対して南側は広大な公共施設エリアである。地図で青色で示されている地域福祉センター,中央公民館,スポーツセンター,町立図書館,森林工芸館,若者交流センター,子どもセンター(認定こども園)などがある。最初,ここを見たときにとくに公民館,スポーツセンター,図書館にかけて,広大な敷地に大きな施設がいくつも建っているので驚いた。後で聞いて分かったのは,駅の南側はかつては林産工場と貯木場となっていたエリアで,山から切り出された木材がここに集められ,加工され駅に運ばれて輸送されたということであるが,その工場はすでになくなり,とくに広大な貯木エリアがこうした公共施設に利用されているということである。「置戸町住生活基本計画」(平成30年 置戸町 p.15)に次の地図と公共施設の写真があったのでご覧頂きたい。
置戸町立図書館の現在
社会教育をベースにした図書館活動
今回,訪問するに当たって改めて図書館問題研究会編著『まちの図書館:北海道のある自治体の実践』(日本図書館協会, 1981)を読んだ。この本により,「置戸」は図書館界において全国区の知名度を得ることになった。入念な事前準備を行い,置戸町での観察や聴き取りを行った上で,図書館活動の歴史と実態を記述し,その意味で小さな自治体での図書館サービスの可能性を十全に表現していると感じた。『まちの図書館』がその後のJLAの町村図書館振興につながる契機になったことも理解できた。JLAの町村図書館活動振興方策検討臨時委員会(長い組織名!)は,図問研の置戸調査のすぐ後の1982年から,全国の町村図書館の現地調査を行い,その結果をもって同委員会著『町村の図書館:そのつくり方と活かし方』(日本図書館協会, 1986)が刊行されている。
だからこそ,『まちの図書館』の最後に,小さな自治体でも『市民の図書館』(1970)で提示されている「貸出,児童サービス,全域サービス」を実施すればこのレベルのサービスが可能になると結論づけていることが気になった。そのことを主張するためには,これ以外の要素はないのか,小さな自治体でこのレベルのサービスがなぜ可能だったのかの考察が必要だが,それが十分ではないと感じたからである。このあとに述べるように,置戸の図書館活動はすべてが社会教育行政をベースにしている。『まちの図書館』では社会教育は図書館活動の前段階にあたり,社会教育の発展を基にして図書館が独自の発達を遂げたと見ている。その見方が必ずしも正しくないことは,行ってみて理解できた。以下,置戸の図書館の発展を先ほどの地域アーカイブの4つの項目の視点を加えながら見ておくが,それは,図書館が資料提供という単一機能では説明できない複合的な作用をもつと考えるからである。(参考:今西輝代教「置戸町図書館の資料とデジタルアーカイブ」蛭田廣一編『地域資料サービスの展開』(JLA図書館実践シリーズ45)日本図書館協会, 2021)
図書館員も含めた戦後の教育関係者は忘れがちだが,戦前の文部省においては学校教育行政と社会教育行政はその覇権を競っていた。というのは,義務教育は初等教育(尋常小学校,国民学校)のみで通常はその高等科まで受けると,多くの人は十代中頃には家業の手伝いなり丁稚奉公や見習い工として使われるなりで,学校から離れることになったからである。そうした青年たちの学習に対応する社会教育施設としての公民館や図書館・図書室は数多くつくられ,またそれらを支える地域教育会が官製でつくられ,地域青年会,青年団,婦人会がそれに連なった。満州事変(1931)以降の昭和戦前期に,それらは国家的な思想統制の道具となっていったのだが,その点ばかりを強調するのも偏った見方になる。地域の祭り,芸能,音楽,演劇,スポーツ,読書などを通じた活動は,上級学校に進まなかった大多数の青年たちにとって数少ない息抜きと交流,そして学びの場だった。盛り場などが少ない農村部においてはとくにそうである。また地区ごとに公民館がつくられその一角に図書室が置かれたところもあった。
敗戦と占領を経て,新憲法の下で戦後教育体制がつくられる。支配する理念が天皇制的原理から西洋的な国民主権に変わり,新たに義務教育が前期中等教育までとなったが,教育の仕組みに大きな変化はなかった。戦後の社会教育行政の方針について,文部省の社会教育課長寺中作雄が推進した「寺中構想」(『公民館の建設-新しい町村の文化施設』1946)が有名である。これは,公民館は社会教育、社交娯楽、自治振興、産業振興、青年育成を目的とし,地域の中心に置かれるべきだとするものである。これに対して,戦前からの社会教育行政を引き継ぐものだと図書館関係者は反発した。彼らは文部省が1949年社会教育法を図書館や博物館を含めた総合的な社会教育行政とすることを意図したものであったのを批判し,その結果、図書館法,博物館法が単独法になったことも知られている。
置戸で社会教育をベースにした町づくりが始まるのもその時期である。置戸町(1950年に町政施行)は,林業で発達し,戦後間もない時期に選択した町づくりの方針が社会教育であった。これは地域の青年会,婦人会に集まった人たちから自然に上がってきた。文部省の寺中構想の考え方をそのままに,社会教育法成立後,すぐに公民館設置条例をつくり,まもなく置戸町を構成する主要地域に公民館を設置した。公民館では青年弁論大会,村民運動会,生活学校,演劇活動などが行われた。そのなかで,公民館に集まった青年たちのなかで,新しい時代の地域づくりのために読書会を開き,公民館に本を持ち寄り図書室をつくる動きがあった。町政に移行した直後の町長選挙で当選したのは,このときに参加していた青年の一人であり,その後、学習活動や文化活動を基盤に据えた町政を実施することが始まった。
公民館図書室はあくまでもスタートラインであって,まもなく図書館法制定直後に図書館設置条例をつくり,ここを町立図書館とすることになった。1964年に文部省農村モデル図書館補助事業を利用して独立館を建設した。建設費総額1800万円のうち,国と北海道が4分の1ずつ,あと起債が4分の1で残りの4分の1が町費だったということである(「置戸の歴史を語る収録 高橋和夫 第2回」『置戸町立図書館館報』27号, 2018, p35)。
つまり,置戸では,新しい時代に向けての町づくりと社会教育,そして図書館が連動していたことが特徴である。そして,そのことは現在に至るまで一貫している。これは,事前に関連文献を読み,町に3日間滞在してじっくりと観察し,関係者と話しをすることで確認することができた。何よりもそのことは,町の中心に充実した公民館,図書館,スポーツセンター(社会体育施設)などの社会教育関係の施設があることから分かる。また,置戸町・置戸町教育委員会『置戸町社会教育50年のあゆみ』(2000)というB5判364ページある分厚い冊子が出され,「社会教育の町置戸」が自己証明的に宣言されている。通常,社会教育は教育行政の一部であるから,自治体史ないしせいぜいが自治体教育史の一部に位置付けられて描かれるだけであるのに,これだけの規模の冊子が編集・執筆されることは異例のことである。町がこの分野に力を入れてきたことを示す。
とくに社会教育と図書館の専門職員について述べておこう。社会教育法では社会教育主事という専門職員の養成および配置についての規定がある。図書館法では司書,司書補の配置について規定している。学校教育と違い,施設自体もその専門職員も設置,配置は義務ではなく自治体ないし教育委員会の裁量に委ねられている。置戸の場合、最初から社会教育主事,司書(補)を配置する方針をとった。公民館と図書館の設置条例制定直後の1954年に,北海道庁網走支庁から資格をもつ社会教育主事を呼び,また,図書館にはかつて読書会活動をして他村の職員をしていた司書補資格をもつ職員に入ってもらった。いずれも専門職を入れる伝統はその後も続いている。一時は4地域の公民館すべてに専任社会教育主事が配置されたという。
現在の図書館サービスの基礎をつくった澤田正春も,北海道大学で社会教育を学び社会教育主事の資格をもって置戸の職員になった人である。1963年に同町職員となり,新館建設時に図書館担当になってから講習で司書資格をとった。同年は『中小レポート』が刊行された年である。彼は司書としてこの図書館を率いて,自動車図書館や中央図書館,公民館図書室を通じてサービスを実践したが,その手がかりは同書であったと述べている。また,1970年の『市民の図書館』も読み,1972年には日本図書館協会からの推薦でブリティッシュカウンシルの基金で英国での図書館視察と研修を経験している。その意味で,日本図書館協会の資料提供と貸出を中心とする図書館サービスの考え方を学んでいた人だった。実際,それらを実行した結果が1970年代に住民一人当たりの資料貸出が日本一を記録して注目されている。
彼は,『まちの図書館』に「<特論>置戸町立図書館からの発言」という文章を寄せ,置戸のサービスは『中小レポート』や『市民の図書館』で示された方針と基本的には一致していて,特段の秘訣はないと発言している。また,1975年に北海道公共図書館協会は彼を中心としたチームで『小図書館の運営』を刊行した。これにより,置戸のやり方が道内の町村図書館に普及し,なかには1970年代から1980年代にかけて,住民一人当たりの貸出数で置戸を上回る実績を上げたところがいくつも出てきたと述べている。彼が述べる置戸町立図書館の特徴は,住民の暮らしに寄り添って,資料提供を忠実にやってきたことによるということである。だが,今回訪問してみて,それだけではないと感じた。澤田の発言は図問研や日図協に対するリップサービスであり,本心は少し違っていたと思われる。
置戸町立図書館が町村図書館のモデルとなりうる理由
置戸が人口がどんどん減っている自治体であるにもかかわわらず,これだけの図書館を維持できている理由を考えてみたい。まず単純な理由としては人口が減っても,総貸出冊数が人口減に対応して減るだけなら,一人当たりの貸出冊数が維持できていると考えることができる。その意味で,現行で一人当たりの貸出し数が14冊ということで,この図書館は(北欧のデンマークやフィンランドなどと似て)地域に完全に根付いた図書館となっていると考えられる。ただし,全体としては貸出冊数が減少していることも確かだから,現状を維持できている要因は別にあると考えられる。それが,第一に社会教育的基盤の存在,第二にそれがもたらす効率的な図書館運営効果,第三に地域意識の集約的提示である。
第一の社会教育的基盤については,これまでにも触れてきたが,澤田氏も現在の司書である森田氏も社会教育を学んだ人であることが重要である。社会教育主事は先ほどの寺中構想にあったように,戦後まもなくは農村地域において地域づくりの中心になることが目指されていた。公民館は人々が地域活動やサークル活動,地域学習などをする場であり,社会教育主事は地域に入っていって,そうした青年たちや住民と濃密に接触して,場合によっては地域づくりを直接サポートする役割を果たすものと考えられていた。実際にこうした考え方を学んだ上で図書館を担当した職員は,司書であると同時に社会教育主事と同様の問題意識をもち地域の問題に取り組む。個々の住民の資料要求だけでなく,地域のイベントや産業振興,行政や学校との連携など,図書館界ではずっと後になって課題解決支援と呼ばれるようになるサービスをいち早くてがける。もちろんその方法は資料を介するわけであるが,地域へのアンテナの張り方が司書とは異なっている。(参考:森田はるみ「地域課題に挑戦する公民館・図書館〜北海道置戸町の場合」小林文人『これからの公民館ー新しい時代への挑戦』国土社, 1999)
このことはもちろん人口数千人の町だから可能だということも言えるだろう。もしかしたら住民一人一人の顔と名前を覚えられるかもしれないくらいの職員と住民の距離の近さがある。町村図書館が公立図書館サービスのモデルとなるとしたら,この点に求められるだろう。これがその10倍(場合によっては100倍)の人口が対象となる市立図書館との違いである。だが,寺中構想と中小レポートが合体したところに生まれるこうした町村モデルがあっても,小規模自治体が多数あるなかで社会教育的な仕掛けをしてきたところは多くない。置戸(ないし周辺のオホーツク地域の町村)の図書館はそうした稀有な例である。
第二に,これによって図書館の効果がより効率的に生みだされる。通常,日本で図書館が地域の課題解決やローカルな情報を提供してくれる場だという理解はほとんどなかった。図書館はあくまでも全国的に流通する出版物を閲覧したり借りたりする場であるというのが一般的な理解である。ところが社会教育と資料提供が組み合わされれば,これが課題解決や地域情報提供の場になる。そのことは公民館を中心とする社会教育から出発して図書館の効果を確認した置戸町の執行部にアピールしたということが言える。そのことは,『置戸町立図書館館報』の27号(2018)に掲載されている,町のウォッチャー高橋和夫氏のインタビューや『同』28号(条例制定70周年記念)(2020)に再掲載の新旧の町長,教育長,館長,図書館協議会委員長9人による座談会(1983年当時)にはっきりと現れている。
とくに後者の座談会は『館報』(9号 1984)掲載のもので,当時の館長澤田が司会をして時系列的な図書館史に現れない図書館設置の事情や当事者の声が赤裸々に伝えられている。社会教育的図書館運営が町の執行部から信頼を得ていた事情がよく分かるものとなっている。次の図書館(生涯学習情報センター)の新館建設につながっていくのもそうした実績があったからだろう。
なお,ここではあまり分析する余裕はないが,図書館のみならず,公民館やスポーツ施設,福祉施設,集会施設などの公共施設がこの地域に集中しているのも同様の理由によると推測できる。過疎地域で,国や都道府県の財政支援に依存する部分が大きいことは全国的な傾向である。これは補助金,地方債,地方交付税の三点セットと言われる。図書館関連の補助金や交付金については,小泉公乃による紹介記事(「公立図書館における補助金・交付金の活用」『カレントアウェアネス』(349), 2021, CA2003, p. 5-8. https://current.ndl.go.jp/ca2003)にあるので参照されたい。
これまで見てきたように,置戸町立図書館については文部省農村モデル図書館整備補助事業,総務省の過疎対策事業債を利用して資金を得て施設をつくった。この記事には,置戸町議会が過疎法における補助対象に図書館を含めるよう政府に要請するなど、図書館復活に向けた活動を展開したことが法改正につながったことに言及している。
他の施設も同様であるが,ここはより積極的に社会教育ないし生涯学習,住民福祉を前面に出して,そうした資金獲得を行ってきた。林業をベースにした町の産業構造が大きく変貌する1980年代以降に,空いたスペースにそうした住民サービスのための施設を建てた。多くの自治体ではそれらの運営がとくに人件費の負担の大きさから指定管理に切り替えることをしてきた。しかしながら,置戸は直営でこれを切り盛りしてきたのは,ひとえに財政負担に見合った効果があると評価されてきたからである。もしかすると町立図書館で指定管理を選ぶところが相対的に少ないのは同様の事情によるのかもしれない。
第三に,その効果の重要な構成要素に地域意識の集約的提示がある。人口2700人の町で蔵書12万冊,職員7人の図書館を運営することの意義は,住民が自らの便益,あるいは福利のために利用することに基づくが,自治体経営論的な視点で見るといかにも効率が悪いという見方も可能である。たとえば,今では車で30分走ると北見市中央図書館がかなり大きな施設と蔵書を周辺の町村にも提供しているから,ここを利用することで住民の図書館要求に応えるという選択も可能である。しかしながら,そうはしなかったからこそこれまでこの図書館が維持されてきたことを見てきた。その場合に,この図書館が地域意識の集約化を代表する場として明示的暗示的に位置付けられてきたのではないか,というのが今回訪問しての最終結論である。
このことを当初,「開拓者意識」という言葉で表現しようと考えていた。明治以降,こうした北海道の自治体において,とくに鉄道が開通して以降に,いろんな地域から人々が入ってきて定着するにあたって,ここを自らの定住地とすると決めた人がいた。それらの人々によって,当該地域の自治意識やコミュニティ意識がつくられる。何よりも,道外なら近世までのムラ社会で,土地とイエを前提とした既存の秩序が支配するのに対して,北海道はすべてを自らつくる必要がある。そのことを開拓者意識と呼ぼうと考えた。だが,開拓者という用語は曖昧で誤解を生みかねない。今回,いくつかの町を訪問して耳にした言葉に,この辺りは明治以降の歴史しかないからこそ,しっかりと歴史を書くことができるというのがあった。北海道開拓の歴史をひもとき,自らの地域の歴史を跡付けようとする考え方はかなり以前からあるようだ。実際,どこの市町村でもかなりしっかりした自治体史が刊行されている。
置戸の場合も同様であるが,ここがそういう意味での歴史意識を積極的に位置付けることができているのは,図書館の地域をベースにした活動と先ほども出てきた高橋和夫氏の存在が大きい。高橋氏は戦後間もない時期の青年読書会に参加し,公民館運動や図書館運動に住民として関わってきた人である。長らく図書館協議会委員を務めた。彼は『置戸タイムス』という週刊新聞を1951年から現在に至るまで出し続け,その意味で置戸の生き字引と呼ばれるような人である。『置戸町史』上下巻,『置戸町議会史』,『置戸町社会教育50年のあゆみ』などの町の正史に当たるものも彼の執筆によるところが大きいとされる。『置戸タイムス』は現在デジタル化され,その一部は置戸町郷土資料デジタルアーカイブで読むことができる。https://adeac.jp/oketo-lib/top/
つまりこういうことである。置戸は戦後間もない時期に公民館に集まった青年たちの新しい時代に対する希望と自治意識が,その後の社会教育行政の重視につながった。社会教育をベースにした図書館は結果として住民一人当たりの貸出数が日本一につながった。だが,それを支えた背景としては社会教育的な働き掛けが常にあったことと共に,地域意識を醸成する作用としてのジャーナリズム(置戸タイムス)とそれを歴史につなげる正史刊行があった。それらはこの高橋氏個人の力で支えられてきた。そして,彼がこの仕事をする際の拠点として図書館の郷土資料の蓄積があったと考えられる。なお,高橋氏が担った地域ジャーナリズムと郷土史は私が考える地域アーカイブの重要な柱となる。図書館はこうした地域的アイデンティティを構築するのに欠くことができないインフラとなるのである。
おわりに
謝辞
追記(2025年7月24日)
2025年7月5日〜6日にかけて,再度,置戸町立図書館を訪問する機会を得た。今回の訪問は主として髙橋和夫さんにお話しをうかがうことを目的としていた。髙橋さんは95歳になられるというが,記憶力や話しぶりはさすがのものがあり,置戸町の「生き字引」そのもののお姿に触れることができた。得られた成果については別途報告することにしたい。
改めて,置戸町立図書館の在り方についての報告に大きな変更点はない。以下では,とくに,「中小レポート」と『市民の図書館』との関係について追記しておいた方がよいと思われることがあるので,2点触れておきたい。
第一に,本文中に「澤田の発言は図問研や日図協に対するリップサービスであり,本心は少し違っていたと思われる。」と書いた点である。もちろん本心は分からないからこれはあくまでも推測である。澤田正春氏は北海道大学で社会教育学の勉強をした人だったが,置戸町に来たときには図書館職員として採用された。すでに社会教育主事の人がいたこともあり,図書館で社会教育をベースにした図書館サービスを担当する職員が求められていたのである。彼はその期待に応える活動を行った。図書館は書物を媒介にしたサービスを行うわけだが,常に町民一人一人の生活を前提にしているということだ。今回うかがった話しで,置戸の農家の人がメロン栽培の本を読んでメロンを出荷したというものがあったが,その後の生産教育や課題解決支援サービスにつながるものが最初からあったことが分かる。
日野の移動図書館ひまわり号は団地の広場や集会室などを訪問したのに対して,置戸のやまびこ号は農村の生業も含めたところにミクロに働き掛けていたということだ。ここに「市民の図書館」(1970)のサービス論理とは異なるものがあったことが分かる。澤田さんは,置戸の図書館長の後,教育長を務め,その後,前川恒雄さんの後の滋賀県立図書館長に就任する。「リップサービス」と書いたのはそのあたりのことである。つまり日図協の図書館振興の路線は変えないことが前提になっていた。しかしながら,彼が置戸でやってきたことは『市民の図書館』とは一致しないもっと泥臭いものだったはずだ。
そのことは第二の点に関わる。先に「置戸は直営でこれを切り盛りしてきたのは,ひとえに財政負担に見合った効果があると評価されてきたからである。」と書いた。この場合の効果とは現在言われるような数値化された行政効果のことではない。行政の担当者によって直接肌身で感じられるようなものである。これは,都市ではなかなか実感できないが,こうした小規模自治体なら十分にありうる。置戸が社会教育をベースにした生活実感に近いレベルでのサービスを提供してきたことがこうした評価をもたらしたと考える。
大都市の住宅地にある日野市と北海道の農村である置戸町では図書館が置かれた条件がまったく異なる。「市民の図書館」の論理は都市部において他者が軒を隔てて住むような住環境を前提にしているから効果も見えるものになるが,それ以上生活に踏み込むことはあまりない。町村の図書館が比較的うまくいく実践事例が報告されやすいのは,まさにこの点にかかわる。つまり人を得られれば,町村の図書館はうまく行きやすい条件があると思われる。とくに北海道は先にも書いたように,近世までの(ややネガティブな意味での)地域意識の縛りがないか弱いことが大きいのである。
先に触れたが澤田さんが中心になって,1975年に『小図書館の運営:北海道の小規模市町村における図書館サービスに関する報告書』(北海道公共図書館協会)という北海道の図書館振興のプランが提案された。この本こそが,中小レポート後の地方小図書館の振興を提言するものだったと思われる。澤田さんが本当に言いたかったことはそこに含まれるのではなかったか。これは,国会図書館デジタルコレクションからアクセス可能なのでぜひご覧いただきたい。









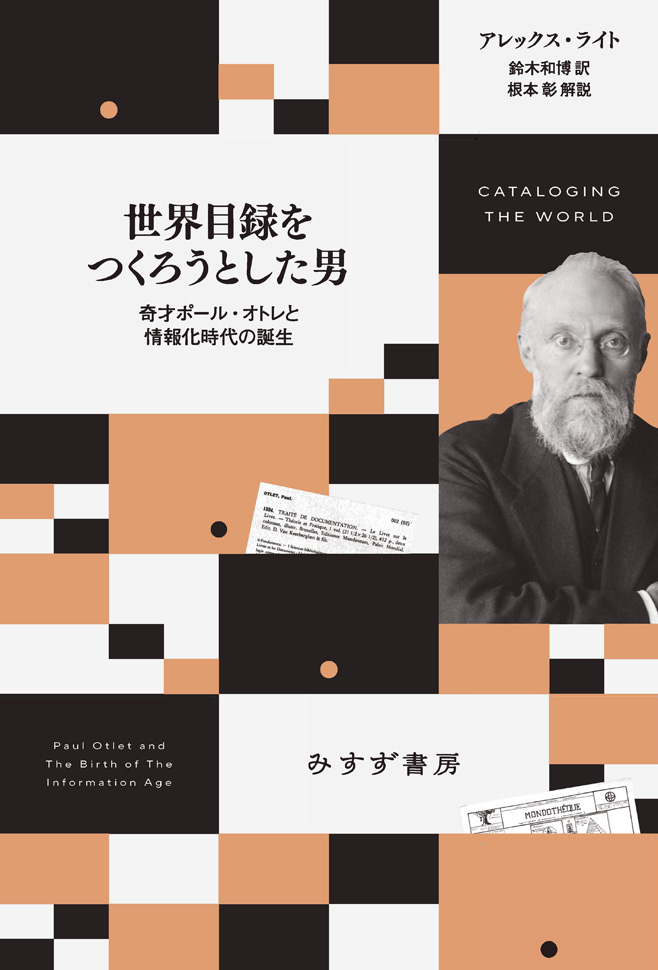



.jpg/2560px-Remington_typewriter_1907_(03).jpg)