毎年,みすず書房から『読書アンケート』という冊子が出され,執筆者として参加している。この一年に読んだ本のなかで他の人に紹介したい本を何冊か挙げるものだが,昨年読んだなかから次の3冊を選んだ。同冊子に書けなかったことを補足しながら(最後の段落),再掲しておく。
1. ピーター・バーク『博学者—知の巨人たちの歴史』井山弘幸訳、左右社、二〇二四年
バークはルネサンス史からスタートした文化史の大家であるが、ここ二〇年の文化史、情報史、学問史を包括した「知識史」の業績にも目を瞠るものがある。人文系の研究者なら一度はチャレンジしてみたいと思ってもなかなか到達できない幅広さが持ち味である。本書は、同著『知識の社会史』二巻本の姉妹編ということだが、ここで言及されている五〇〇人の「博学者」は、彼の言う「博学」が、同時代の横断的な知の俯瞰を可能にする思考法や方法を新たに提示した人たちであり、彼自身の博学の賜だったことが分かる。訳書について、カヴァーが表紙全体を覆っていない手法をとることでハードな手触りが楽しめる造本デザインの良さと、索引も含めて原著に忠実に訳されている点についても付け加えておきたい。
この本の口絵には13人の「博学者」の肖像が掲載されているが,そのなかにドキュメンテーション運動の創始者ポール・オトレがいる。日本では一般的にはほとんど知られていなかった人であったが,昨年,彼の評伝であるアレックス・ライト(鈴木和博訳)『世界目録をつくろうとした男』(みすず書房)を出してもらってようやく少し理解されるようになった。西欧でも日本でも「博学」は古くさい知の方法とされてきたように思われる。(村上陽一郎氏が毎日新聞の書評で,オトレをなぜこんなところに取り上げるのかという筆致で書いているのが気になっている—無料版の最後の部分 )しかしながら,博学者500人を次々と紹介するバークの手法は,生成AIとどう違うのかと考えてみることも一興だろう。
2. マシュー・ルベリー『読めない人が「読む」世界—読むことの多様性』片桐晶訳、原書房、二〇二四年
近年、「読む」ことの再定義が求められている。子どもたち(大人も含め)がスマホやタブレットを常時抱え参照することで、「読めなく」なっているとも言われ、これを実証し、またその危険性を訴える本も多数出ている。他方、二〇二三年上半期の芥川賞受賞作市川沙央『ハンチバック』は重い身体障害による「読めない」ことの救済を訴えるもので、それゆえ著者の主張が世に知られることになった。市川も登場する『現代思想』二〇二四年九月号の「読むことの現在」では多種多様な場の「読み」が列挙されている。
ルベリーの本書は、「読む」行為の多様性を論じる。著者は定型的な読字を妨げる、難読症(ディスレクシア)、過読症(ハイパーレクシア)、失読症(アレクシア)、認知症(ディメンシア)、共感覚(シナスタジア)、幻覚(ハルシネーション)の六つの症例から生まれる読みの困難さに読みの可能性をも見いだそうとする。ここに多用されているカタカナのルビは、原文を定型としてそれが読めない日本人読者のための読字の工夫と見ると、翻訳の読字論から日本文化論への別のアプローチを示唆する。編集上のことについて一言すれば、原著にある索引が省略されている点と注に瑕疵が散見される点が残念である。
「読む」「読書」「読解」「読字」...などは今ホットな話題である。読むことに対するバリアが身体的なもの,物質的なものから心理的なもの,社会的なものまで多様に存在することについてこれまでも指摘されてきた。しかしここで参照した『現代思想』の特集記事では,法律条文は一般の人には読めないとか,詩を読むとは言葉とどう向き合うことかとか,物理学者が哲学書を読むときの脳内対話とか,ベトナム人技能実習生の言語生活に日本語文書は位置付けられていないとか,といった論考を目にし,さらにカタカナで表現された〇〇症というレッテルを目にして,何だかくらくらとめまいがしてきた。私たちが前提としてきた,文字社会ないし書字社会は幻影にすぎないのかと。
3. ジェフリー・ロバーツ『スターリンの図書室—独裁者または読書家の横顔』松嶋芳彦訳、白水社、二〇二三年
スターリンが残した二万五千冊の蔵書には書き込みが多数あり、それらの一部は現在デジタルで公開されている。これまでも多数のロシア、ソ連の外交・軍事政策の書を著してきた著者は、今回、そうした書き込みを元に「複数の顔をもつ男」スターリンの実像に迫ろうとした。まず、ボリシェビキはマルクス、エンゲルス、レーニンの正統的な社会主義思想を継承するために出版物を重視するという伝統をもっていたが、スターリンは、革命の理論と実践を結びつけるためにそれらを読むことで率先して実行したとする。さらには東西の軍事史、政治史の著作に学ぶだけでなく、政敵の弱点を知るためにその著書を分析的に読み、軍事侵攻の手がかりを各国の経済書や地理書を読むことで得ようとした。読んだ際のスターリンの心奥のつぶやき、賞賛と非難、嘲りなどが書き込みにそのまま現れている。本書は、独裁者の読みの記録が新たな歴史の読みにつながるという例を示している。
原書には事項(主題)索引を含むアルファベット順索引があるのに、本訳書には人名索引とタイトル索引しかない。なお、索引についてしつこく言及したのは、昨年取り上げたデニス・ダンカン『索引 〜の歴史』に依り、日本でもこうした専門書には事項索引を含めたきちんとした索引を付けてほしいと考えるからである。
今,知識組織論研究会で索引ないし主題という問題に取り組んでいる。一定の言説からメタデータを取り出すことや,タグとかハイパーリンクをつけるということが行われている。それは何のためにやっているのか。専門書には巻末索引が必要だと言われてきたが,上で引用したダンカンの本にあるような人手でつけられる索引をどうやってつけるのか。テキスト中の「重要語」にアンダーラインを引いてそれを索引語にするという定型的なやり方にどれほどの意味があるのかというような問題に一応の回答はある。しかし,それはどのような読み手を想定してつけるのか,何が重要語なのか,本文中にない用語は索引語にできないのか,などと考え出すとけっこう難しい問題に行き着く。
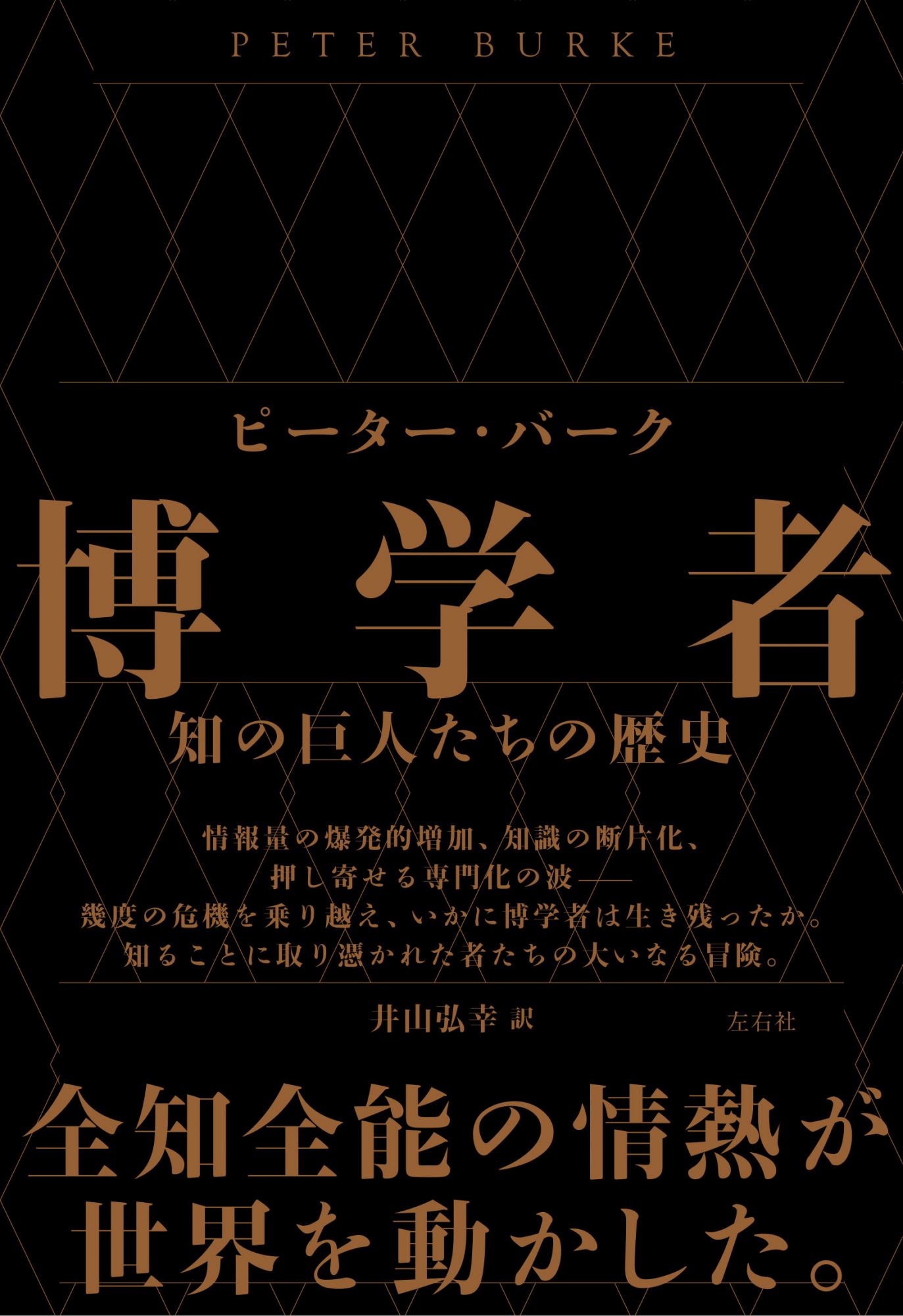

0 件のコメント:
コメントを投稿